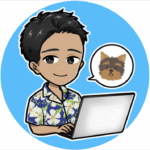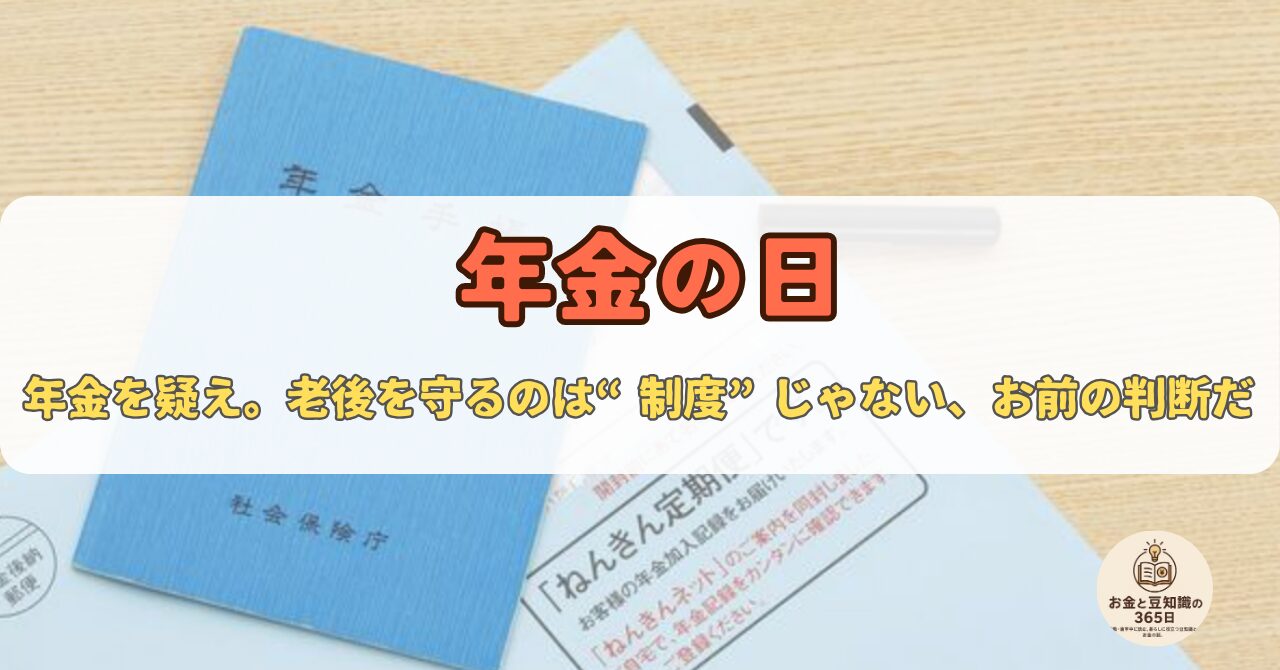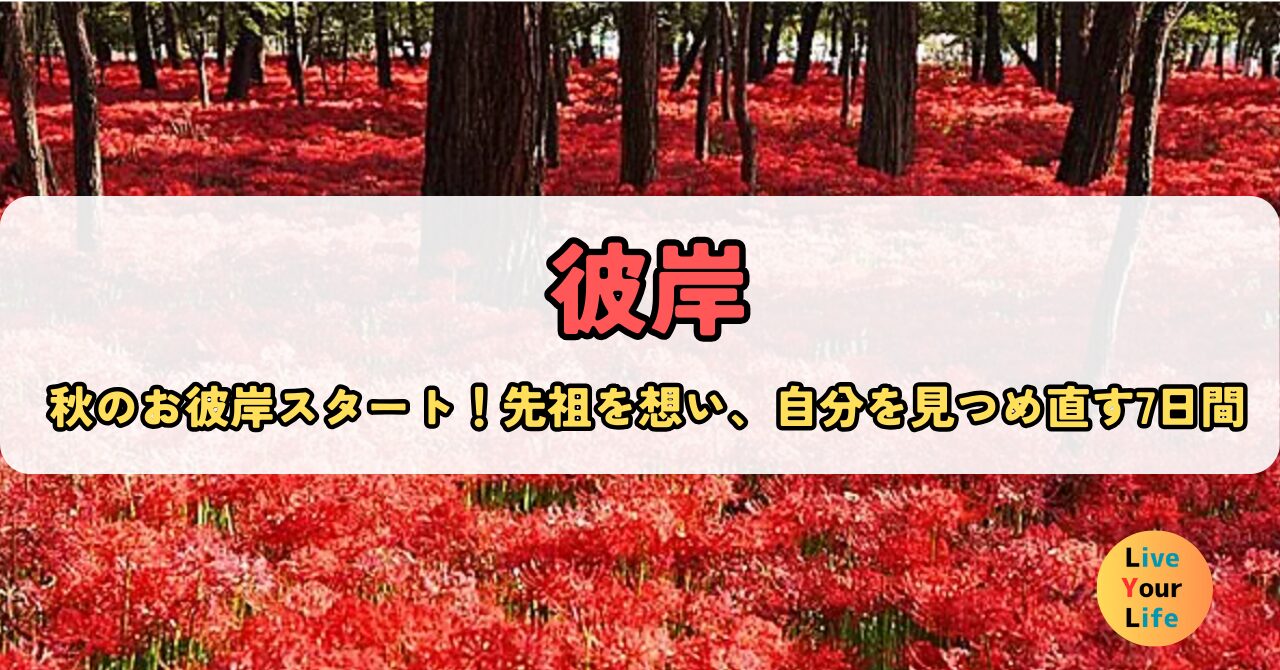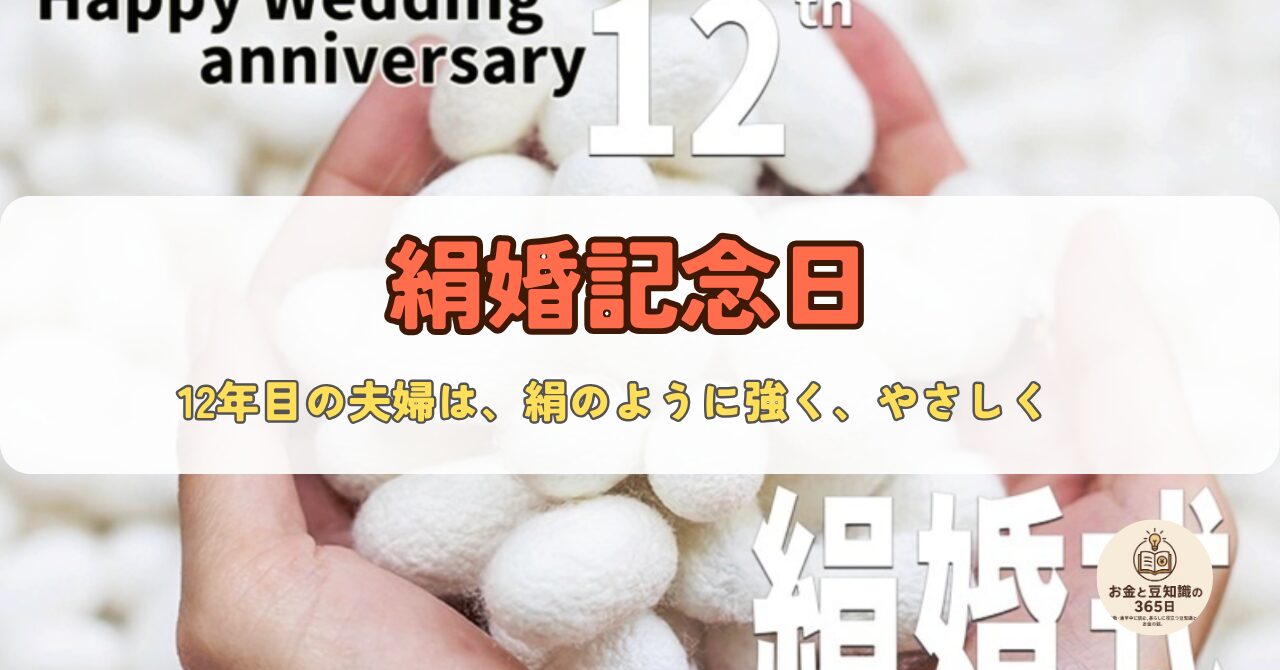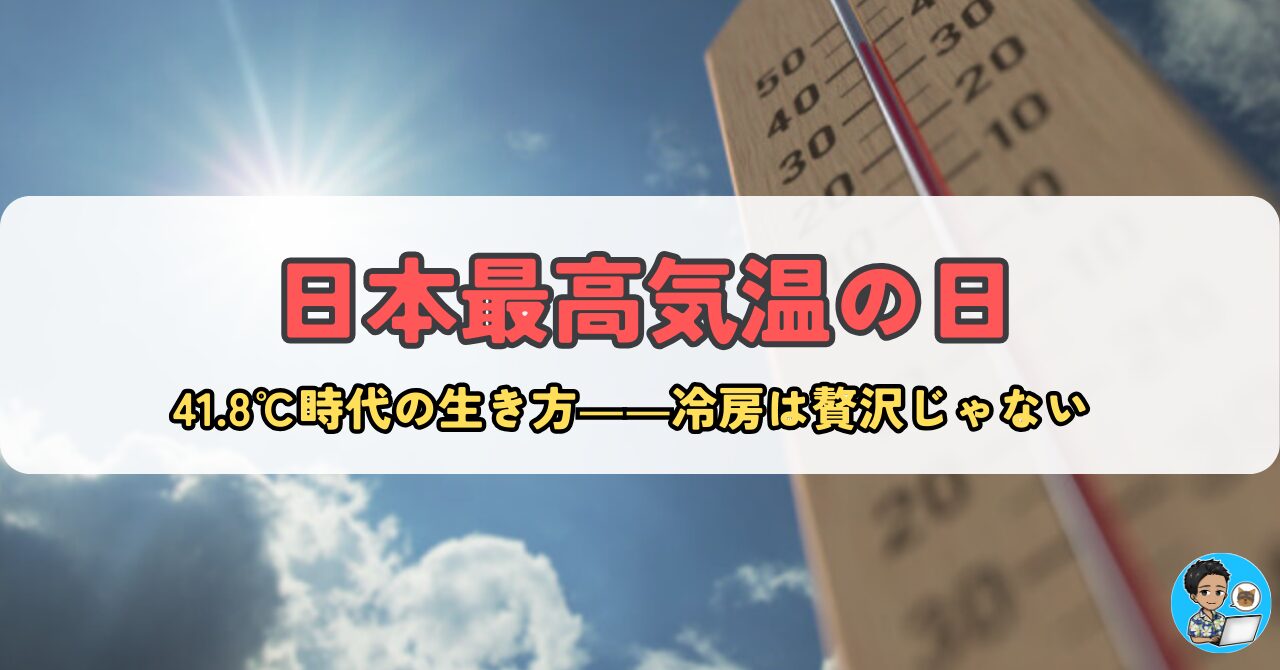9月19日【育休を考える日】父も母も、もっと自然に育休を選べる社会へ

こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日9月19日は、「育休を考える日」です。
育児休業、略して「育休」。子どもが生まれたら母親だけでなく父親も取得できる制度ですが、実際どう使われているか、周りの意識はどう変わっているか――。今日は、育休の現状と未来について、少し立ち止まって考えてみませんか?
由来と制定の背景
- 「育休を考える日」は、積水ハウス株式会社が2019年に制定した記念日。
- 日付は「9月19日」。語呂合わせで「育(19)休(9)」と読むことから決まりました。
- 日本記念日協会にも認定登録されており、企業・団体を巻き込んで「育休取得を考えるきっかけ」を社会的に作ることが目的です。
現状と取り組み:「IKUKYU.PJT」ってなに?
「育休を考える日」とともにスタートしたプロジェクト
- 「IKUKYU.PJT(育休プロジェクト)」は、積水ハウス株式会社が2019年にスタートした社内外の取り組みです。
- 目的は、男性社員の育児休業取得の促進と、企業文化の変革。
単なる「制度の提供」ではなく、
“育休を取りたくても取りにくい”社会の空気や職場の文化を変えることがこのプロジェクトの真の狙いです。
実際にどんなことをやってるの?
- 「イクメン休業制度」を導入
→ 子どもが3歳未満の男性社員に対し、1か月以上の育児休業を必須化。
→ 育休取得を「努力目標」ではなく「標準行動」として制度化。 - 管理職への働きかけ・研修
→ 育休を“推奨する側”のマインド醸成も同時に実施。
→ 部署単位での人員調整・カバー体制づくりなども支援。 - 外部への発信・共創
→ この活動は社内にとどまらず、同様の取り組みに賛同する企業・自治体とネットワークを形成。
→ 2025年時点では、174社・団体が「育休を考える日」プロジェクトに参加。
取り組みの成果
- 積水ハウスでは、2018年から男性社員の育休取得率100%を実現。
- 多くの男性社員が“実際に1か月以上”の育休を取り、復帰後も職場にスムーズに戻れる環境が整えられている。
- 特に建設業界のように「育休取得率が低い」とされていた分野でのこの実績は、社会的にも高い評価を得ています。
社会への波及効果
- このプロジェクトを通じて、
→「男性が育休を取るのは“特別”ではなく“当然”」という価値観の転換が促進。
→ 育休を通じて得た“子育て視点”が、社員の人間力やマネジメント力の向上にもつながるという副次的効果も。 - 育児と仕事の両立において、「個人の選択」と「企業の支援」が両輪で進むことの重要性を社会に広める起点となっています。
今後の広がりに期待!
「IKUKYU.PJT」は、単なる一企業のCSR活動ではなく、
“誰もが子育てと仕事を両立できる社会”へのモデルケース。
これからもっと多くの企業がこの取り組みに参加し、
育休を「考える」「取れる」「応援し合える」文化が、社会のあたりまえになっていくことが期待されています。
「育休を考える日」が持つ意味と、私たちの課題とは?
育休を“考える”こと自体が、すでに第一歩
「育休を考える日」という名前には、
“とって当然”でもなく、“とらなきゃダメ”でもない、
「考える」という余白があることが重要な意味を持っています。
- 「自分やパートナーにとって、育休ってどういう意味があるだろう?」
- 「会社の制度は?職場でどう調整できるだろう?」
- 「育児と仕事、どっちを優先するかじゃなくて、どうバランスを取る?」
…こんな風に、一人ひとりが**「育休を自分ごと化するきっかけ」**として、この日があるのです。
男性育休取得の“壁”は、制度より「空気」
日本では、育児休業制度そのものは整ってきています。
それでも現実には、男性の育休取得率はまだまだ低水準。
その理由は?
- 「周囲に迷惑をかけるんじゃないか」
- 「復帰後の評価が下がるのでは?」
- 「前例がないから不安」
つまり、“制度はあるけど、使いにくい”。
これは制度の課題ではなく、“職場の空気”という文化的課題なんです。
企業と社会に求められる変化
この記念日は、企業にとっても行動のきっかけ日になります。
- 育休取得を推奨するだけでなく、取得しやすい職場環境の整備
- 管理職への研修・意識改革
- 育休後の“キャリアの継続性”をどうサポートするか
制度を「作る」よりも、「どう根付かせるか」が問われる時代に入ってきています。
育休を「とる・とらない」ではなく、「話せる社会」へ
この記念日は、「育休=育児を休む」というよりも、
**家族や働き方、生き方について“立ち止まって話せる日”**でもあります。
- パートナーと将来を考える
- 職場で同僚と価値観をシェアする
- 子どもを育てることが、仕事にも人生にも“プラスになる”と気づく
そんなきっかけを持てる社会こそが、
育休の“次のフェーズ”なのかもしれません。
ちょこっと豆知識:「育休」にまつわる“へぇ〜”な話
【1】日本の育休制度は、実は世界トップクラス!?
実は日本の育児休業制度、世界的に見てもかなり手厚いことをご存じですか?
- 育児休業期間:男女ともに原則「子が1歳になるまで」(条件により最長2歳)
- 育休中の給付金:最初の6か月は「賃金の67%」支給、その後は50%
- 企業によっては、さらに上乗せ支給あり!
つまり、「制度だけなら世界でも指折り」レベルなんです🇯🇵
…が、“使いやすさ”はまだ課題多し。宝の持ち腐れ状態!?
【2】男性育休、実は“取った人の9割”が「取ってよかった」と回答!
内閣府の調査によると、育休を取った男性の約90%が「取ってよかった」と回答しています。
よくある理由は…
- 子どもとの絆が深まった
- 妻への理解が深まった
- 仕事へのモチベーションが上がった
取った人の満足度が高いのに、**周りが取ってないと“取りづらい”**というのが大きな壁なんです。
【3】海外では「パパの育休」が当たり前な国も!
- スウェーデンでは“パパクオータ制”といって、父親が育休を取らないと支給額が減る制度まであるんです!
- 韓国では男性の育休取得率が40%以上!制度改善の影響で年々増加中。
つまり、「育休=女性だけのもの」ではないという認識は世界的に進んでいます🌍
日本も今、その変革期に入っているのかも!
【4】積水ハウスの「イクメン休業制度」は男性育休“全員取得”が目標!
「育休を考える日」を制定した積水ハウスでは、
3歳未満の子どもを持つ男性社員に1か月以上の育休を必須化。
その結果、男性の育休取得率は100%を達成。
建設業という“取得しにくそう”な業界でこの実績は、まさに先進的!
【5】「育休を考える日」は“制度を使わない人”にも大切な日
この記念日は、育児中の人だけのものではありません。
- これから親になるかもしれない人
- 同僚が育休を取る予定の人
- 働き方について考えたいすべての人
つまり、誰にとっても“働き方”と“人との関係性”を考える日なんです。
まとめ:育休を“誰かのこと”から“自分の選択肢”へ
「育休を考える日」は、
子育て中の人だけに向けられた記念日ではありません。
今まさに育児に関わっている人も、
これから親になるかもしれない人も、
誰かの育休をサポートする立場にいる人も――
みんなが一緒に“育休”という選択肢を考え直せる日です。
「育休をとる」とは、
- 家族と向き合う時間を選ぶこと
- 社会と調和する働き方を見つけること
- そして、未来の子どもたちに“あたたかい社会”を残すこと
少しだけ立ち止まって、
「自分だったらどうしたいか」「何ができるか」を考えるだけでも、
社会は少しずつ変わっていきます。
今日のあなたの“気づき”が、
明日のだれかの“働きやすさ”につながっていく――
そんな記念日になったら素敵ですね。
📢「今日は何の日」では、日常を少し豊かにする気づきを毎日お届け中!