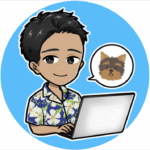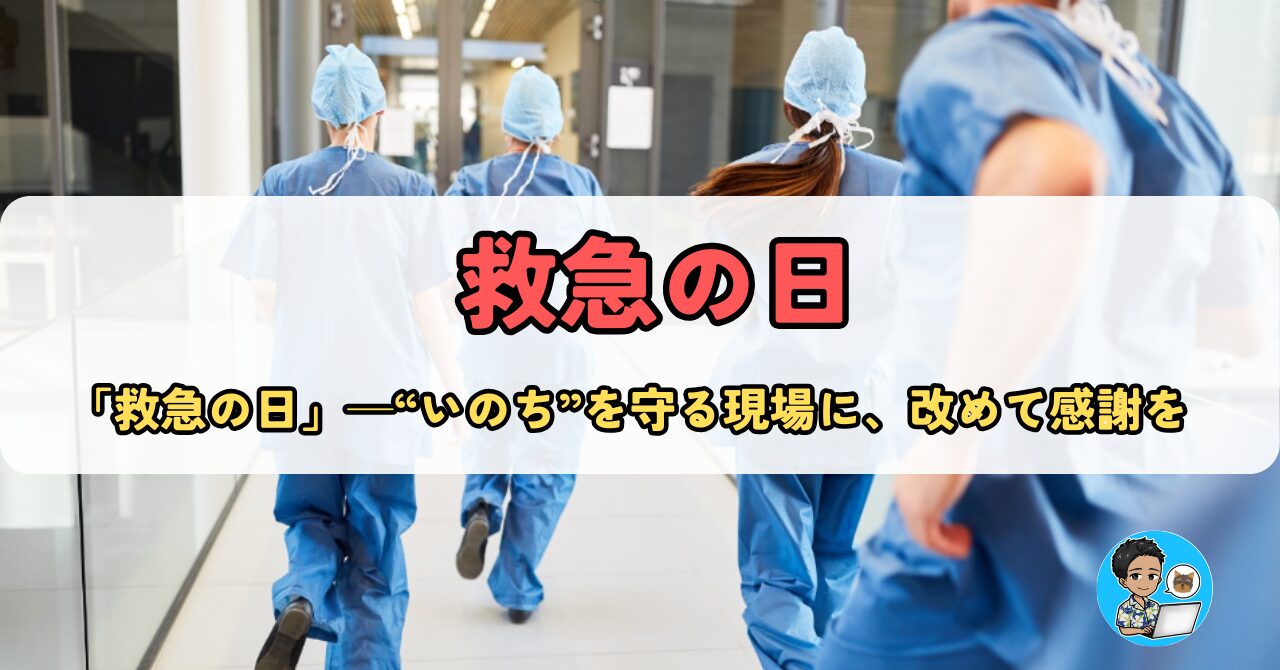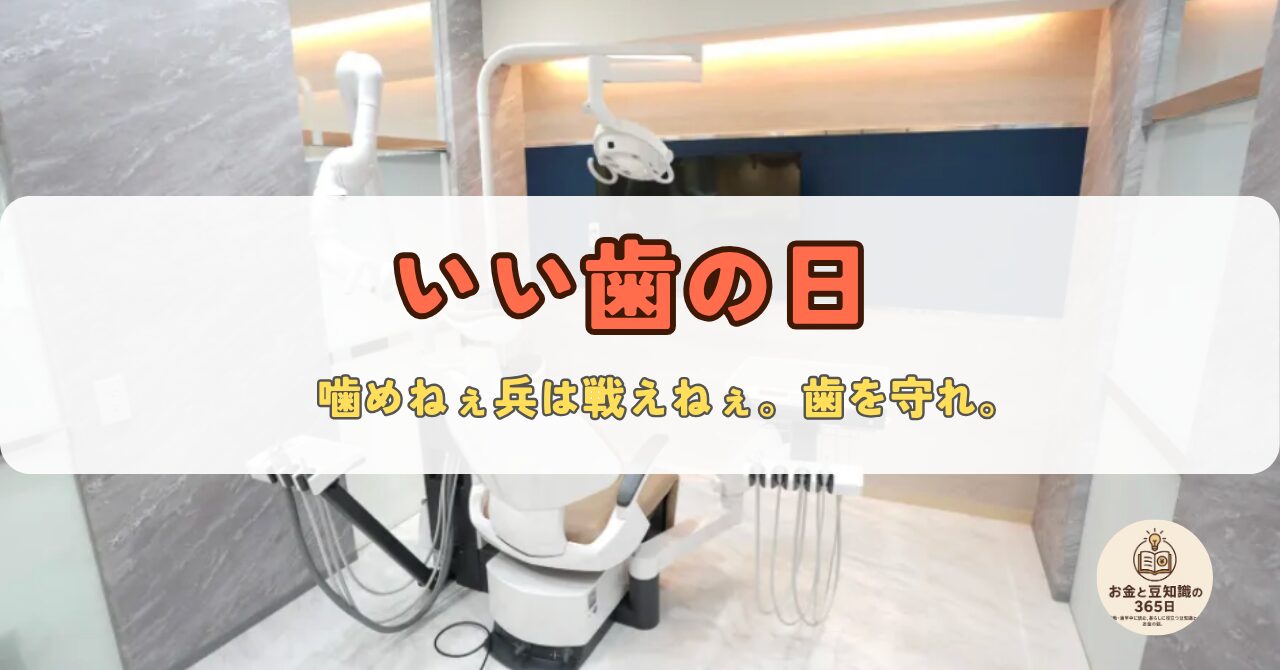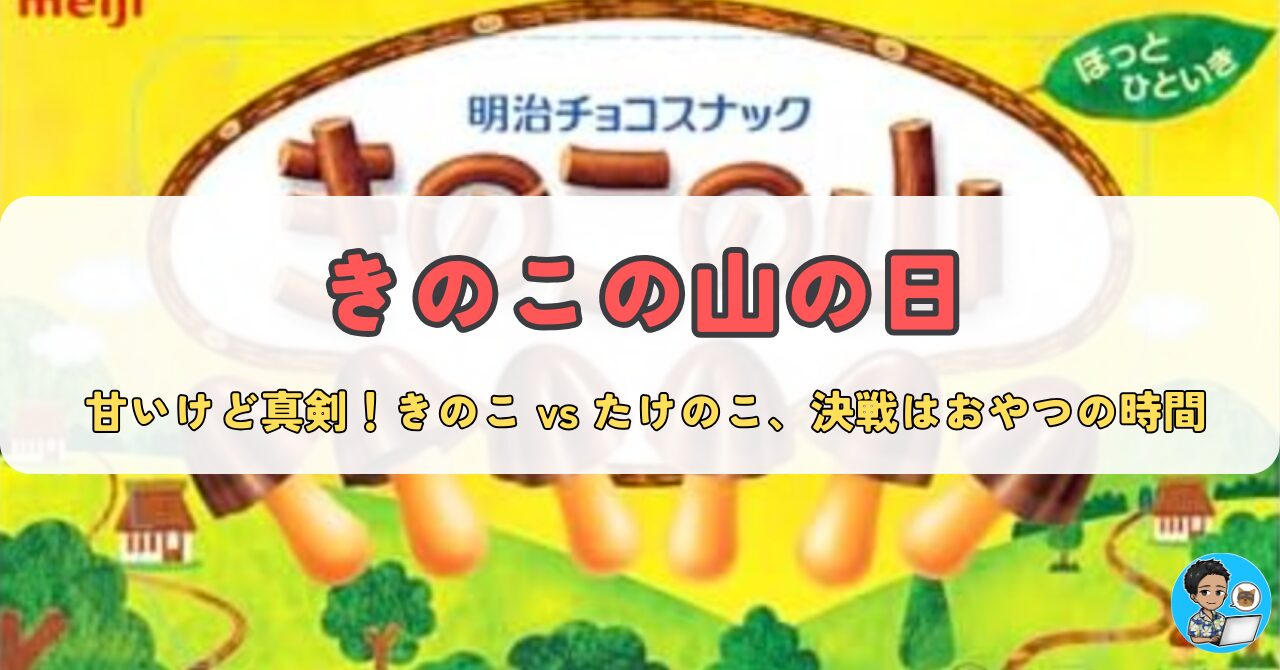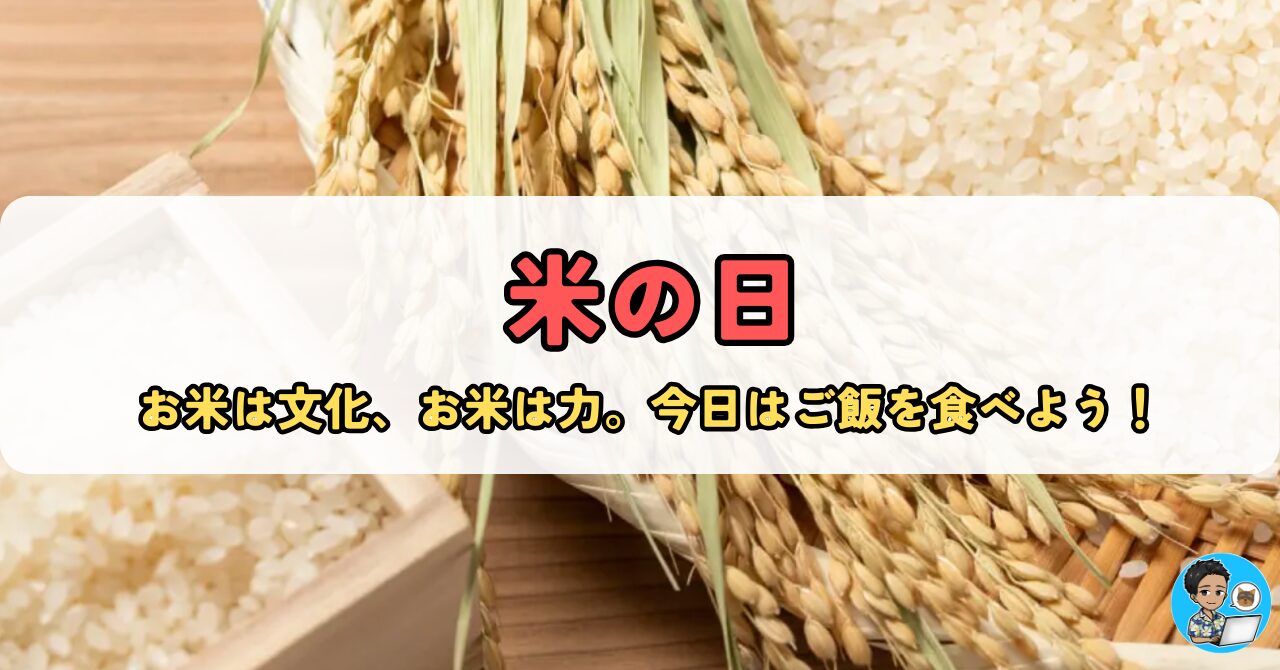9月21日【彼岸】昼と夜が同じ長さになる特別な時期――先祖と心がつながる瞬間
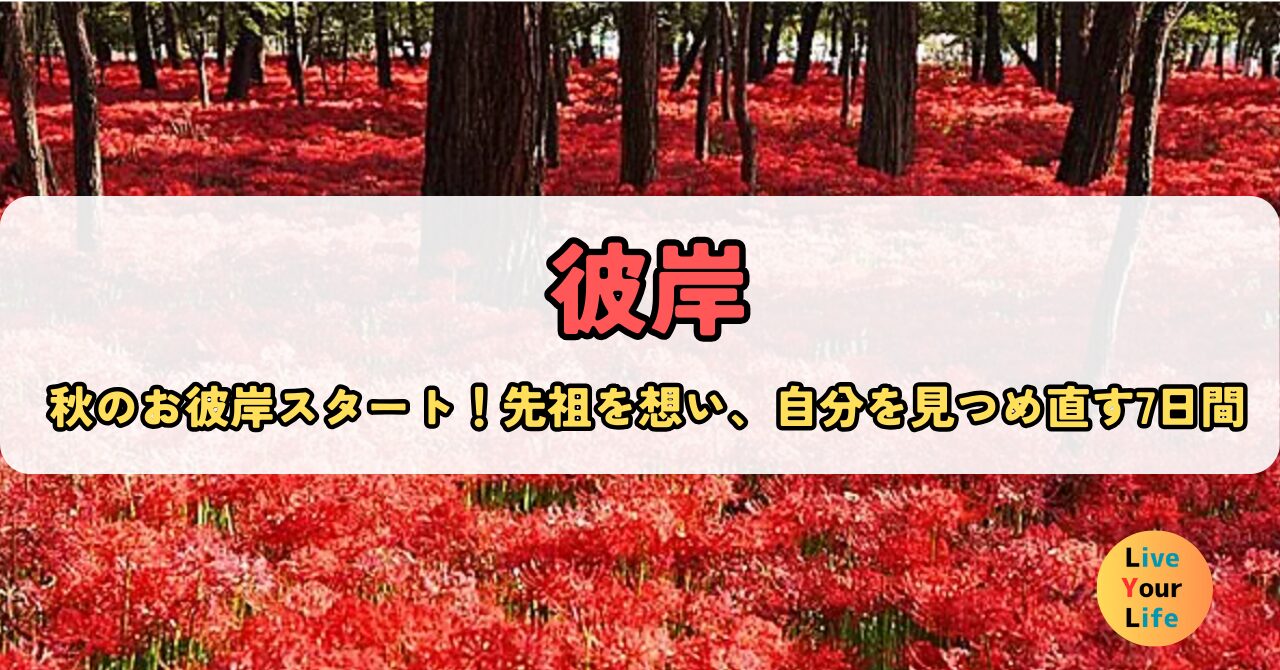
こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日9月20日からは、「秋のお彼岸」が始まります。
「お彼岸」といえば、墓参りやおはぎを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
でもそもそも、なぜこの時期に「彼岸」という行事があるのか――今日はその背景と意味を一緒に考えてみましょう。
由来と制定の背景
1) 言葉のルーツと思想背景
「彼岸」は仏教語「到彼岸(とうひがん)」の略で、サンスクリット語 pāramitā(波羅蜜多=悟りの岸へ到る修行)に由来します。現世=此岸(しがん)から、悟りの世界=彼岸へ“渡る”という比喩がベースです。
補足:日本の「彼岸」行事はインドや中国の仏教には見られず、日本固有の信仰(太陽・祖霊観)と仏教が結びついて成立したとする見解が有力です。
2) 最古の記録:国家レベルの「彼岸会(ひがんえ)」
史料上の初出は平安初期・延暦25年(806)。『日本後紀』によれば、崇道天皇(早良親王)の怨念鎮魂のため、春分・秋分の前後7日間にわたり『金剛般若波羅蜜多経』を読み上げる法会が行われ、太政官が全国の国分寺にも同様の実施を命じて“恒例”となりました。これが後の「彼岸会」に発展します。
その後、文応元年(1260)には亀山天皇が六斎日と春秋彼岸に殺生を禁じたと伝わり、王朝儀礼から庶民へと習俗が広がっていきます。
3) なぜ“春分・秋分”なのか:西方浄土と太陽
春分・秋分は太陽が真東から昇り真西に沈む日。浄土教では極楽浄土は西方にあるとされ、この日は此岸と彼岸がもっとも「通じやすい」と考えられました。そこで真西を拝し先祖に思いを馳せる慣習が生まれ、供養の行事(彼岸会)が定着しました。
4) 祝日の“制定”と戦後の位置づけ
戦前の秋分(および春分)は、宮中で歴代天皇・皇族の霊を祀る「秋季(春季)皇霊祭」として扱われました。戦後の1948年、国民の祝日に関する法律で宗教色を離れて「秋分の日」「春分の日」が新設され、その趣旨はそれぞれ――
- 春分の日:自然をたたえ、生物をいつくしむ。
- 秋分の日:祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
と明文化されました。日付は天文学上の“春分日/秋分日”に基づき、毎年国立天文台の暦要項で確定します。
現状と取り組み
お彼岸には多くの人が墓参りに出かけ、仏壇を整え、お供え物をします。秋のお彼岸では、小豆の赤色で魔除けを意味する「おはぎ」が定番のお供え物。

また、仏教ではお彼岸の7日間を「六波羅蜜」を修する期間ともしています。布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧を一日一つずつ実践し、心を見つめ直す機会とされてきました。
近年では「お彼岸=家族で集まるきっかけ」として、世代を超えて交流する時間を大切にする家庭も増えています。
彼岸が持つ意味・課題
彼岸の大切さは、単なる伝統行事を超えて「命をつなぐ意識」を育む点にあります。
- 先祖供養を通して“自分があるのはご先祖さまのおかげ”という感謝の心を持つこと
- 家族や親戚が集まり、絆を深める時間を持つこと
- 日常の忙しさから離れ、心を静めて自己を見つめ直すこと
一方で、核家族化や都市生活の広がりによって「墓参りに行けない」「お彼岸を意識する人が減っている」という課題もあります。
これをどう次の世代に伝えていくかが、今後の社会にとってのテーマといえるでしょう。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
季節と呼び名の違い
- 春は「牡丹」にちなみ ぼたもち(牡丹餅)、秋は「萩」にちなみ おはぎ(御萩) と呼ばれます。
- 実際には同じ「もち米+あんこ」のお菓子ですが、季節の花に合わせて名前を変えるのが日本らしい粋な文化。
世界でも珍しい、日本独自の行事
- 「彼岸」は仏教語がベースですが、春分・秋分に供養を行うのは日本だけ。
- インドや中国、韓国などの仏教圏には同じ習慣はなく、日本独自に成立した仏教行事と考えられています。
太陽と西方浄土のリンク
- 春分・秋分は太陽が真東から昇り真西に沈むため、極楽浄土(西方浄土)に最も近づける日と信じられました。
- このため、古くから西を向いて拝む「日想観(にっそうかん)」が盛んに行われました。
戦後に“祝日化”した歴史
- 戦前は「春季皇霊祭」「秋季皇霊祭」という宮中祭祀の日でした。
- 戦後の祝日法(1948年制定)で宗教色を薄め、春分・秋分は国民の祝日に。
- 趣旨はそれぞれ
- 春分の日:自然をたたえ、生物をいつくしむ日
- 秋分の日:祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日
となりました。
あんこの違い
- 春の「ぼたもち」=冬越しの硬い小豆を煮て“こしあん”に。
- 秋の「おはぎ」=新豆の小豆をそのまま使うため“つぶあん”に。
- 季節によって小豆の状態が違うことから、あんこのスタイルも変わったといわれます。
お墓参りの文化
- 「彼岸に墓参りする習慣」は江戸時代から庶民に広がったもの。
- 農閑期で移動がしやすく、また季節の節目として先祖に報告・感謝する意味が強調されました。
まとめ
お彼岸は、単なる季節の行事や「おはぎを食べる日」ではありません。
その背景には――
- 仏教の「此岸から彼岸へ」という思想
- 太陽の動きと西方浄土信仰
- 国家行事から庶民の習俗へと広がった歴史
- 春秋それぞれに込められた季節感や食文化
が折り重なっています。
現代では核家族化や都市生活で「お墓参りに行けない」という課題もありますが、
本質は 「ご先祖に感謝し、いまを生きる自分を見つめ直す時間」 を持つことにあります。
9月20日から始まる秋のお彼岸――
ぜひこの機会に、家族で語り合ったり、静かに自分の心を整えたりしてみませんか?
過去から未来へ、命と心をつなぐ。
お彼岸はそのための大切な節目なのです。