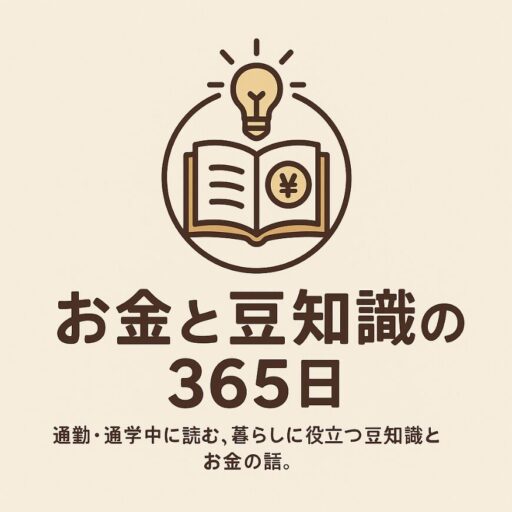こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日9月25日は、「10円カレーの日」です。
通常なら数百円〜千円以上するカレーライスが、たった10円で食べられる――。
ユニークでありながら、実は深い社会的な背景や想いが込められた日なのをご存じですか?
由来と制定の背景
「10円カレーの日」は、東京・日比谷にある老舗レストラン 日比谷松本楼 が制定。
- 1971年(昭和46年)11月19日、松本楼は学生運動による放火で焼失。
- しかし、多くの市民や常連客の寄付・励ましで、わずか半年後の 1973年(昭和48年)9月25日 に再建オープン。
- この「支援への感謝」を形にするため、開店記念日に“ワンコインならぬワンコイン以下”の 10円カレー を提供するイベントを始めたのです。
以来、毎年9月25日が「10円カレーの日」として知られるようになりました。
「10円カレーの日」の現状と取り組み
1. 毎年9月25日、松本楼の恒例行事
- 会場:日比谷公園内「松本楼」本店(洋食の老舗)
- 開催日:毎年9月25日(再建記念日)
- 提供内容:伝統の欧風カレーを10円で提供(数量限定 約1,000〜1,500食)
- ルール:来場者は最低10円を支払い、寄付を添えることが通例
2. チャリティ活動としての側面
- 当初は「再建に協力してくれた人々への感謝」から始まりましたが、現在は チャリティイベントとして定着。
- 寄付金はその年ごとに 社会福祉団体・災害復興支援・子ども関連NPOなどへ全額寄付。
- 毎回、数百万円単位の寄付金が集まる規模に成長しています。
3. 行列は社会的風物詩
- 毎年、多くの人々が開店前から長蛇の列を作り、ニュースでも報じられる名物イベント。
- 「安いから」ではなく、「伝統に参加したい」「寄付をしたい」「支援の輪に加わりたい」という動機の人も多いです。
- 参加者の世代は幅広く、親子連れ・観光客・サラリーマン・学生まで集まります。
4. コロナ禍と開催の工夫
- 2020年・2021年:新型コロナの影響で中止。
- 2022年以降:感染対策を講じながら段階的に再開。
- 食券方式の導入
- ソーシャルディスタンスを意識した行列整備
- ただし「以前のように大規模に集まるのは難しい」という課題も残っています。
5. 社会貢献とブランド力
- 10円カレーは松本楼の「看板イベント」であると同時に、CSR(企業の社会的責任)活動の象徴。
- 企業主導ではなく“市民参加型の寄付文化”として広まっており、
- 「食べて寄付する」シンプルさ
- 誰でも参加できる気軽さ
が、長年愛される理由になっています。
6. 今後の課題と展望
- 継続性:物価高や人件費増加のなか、10円という象徴価格を守るために工夫が求められる。
- デジタル化:オンライン寄付や事前予約制の導入など、新しい形での運営も模索される可能性。
- 社会的意義の継承:ただの“安いカレーイベント”ではなく、**「感謝と社会貢献の文化」**として若い世代に伝えていくことが大切。
「10円カレーの日」は、単なるサービスイベントではなく、
“感謝”と“寄付文化”を広げる社会的取り組みとして発展し続けています。
その姿は、地域と企業、市民が支え合う象徴とも言えるでしょう。

10円カレーの日が持つ意味・課題
- 「支えてくれた人への恩返し」
松本楼の再建は市民の善意によって成り立った。その感謝を「10円カレー」で形にしている。
- 「食の力で社会をつなぐ」
誰もが気軽に参加できるチャリティ活動として、寄付文化を広げる役割も。
- 「イベントの継続と変化」
時代とともに来場者数や寄付額は変化しており、持続可能な形での開催方法が今後の課題。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
1. なぜ“10円”なの?
- 「10円」は再建時の感謝の象徴。本来は原価割れですが、“誰でも支払える最小限の金額”として設定。
- 実際はほとんどの人が100円、500円、1,000円以上を寄付しており、10円はあくまで「参加のきっかけ」にすぎません。
- 一杯のカレーが寄付文化の入り口になっているのがユニークです。
2. 開催初年から大行列!
- 再建オープンの1973年から続く恒例行事で、初回から数百人の行列ができたそうです。
- 現在では 1,000〜1,500食限定。午前中に完売することも多く、「並ばないと食べられないカレー」として知られています。
3. 寄付額は数百万円規模
- 来場者数と寄付の合計は、毎年数百万円単位になることも。
- 集まったお金は 災害被災地支援や社会福祉団体への寄付に使われています。
- ただ食べるだけでなく、食べること自体が社会貢献になる仕組みです。
4. 松本楼は“カレーの老舗”
- 松本楼は1903年創業の老舗洋食レストランで、「日本にカレー文化を広めた店の一つ」とも言われます。
- 明治期から洋食と共にカレーを提供しており、その伝統の味を「10円」で味わえるのはこの日だけ。
- グルメイベントとしても鉄板の人気を誇ります。
5. 芸能人や著名人も関わった
- 松本楼の再建時には、当時の首相・田中角栄や文化人も支援したエピソードが残っています。
- 「市民に愛された店を取り戻そう」という思いが広がり、寄付の輪が全国から集まったことも“10円カレー”誕生の背景になっています。
6. コロナ禍での中止と再開
- 2020・2021年は中止。ファンから「今年はやらないの?」と多くの声が寄せられました。
- 2022年から再開し、整理券配布や行列制限など感染対策を実施。
- このように、続けるために形を変えてきた柔軟さも長寿イベントの秘訣です。
7. 海外からの観光客にも人気
- 「10円カレー」はガイドブックやSNSでも紹介され、外国人観光客が訪れるケースも増えています。
- 「Japan’s famous 10 yen curry」として英語圏メディアに取り上げられ、国際的な知名度を得ているのも面白い点。
まとめ
「10円カレーの日」は、ただ“安くカレーを食べられる日”ではありません。
それは、市民に支えられて再建した老舗レストランが、感謝を形にした特別な日です。
たった10円のカレーに込められているのは、
- 支えてくれた人々への恩返し
- 誰でも気軽に参加できる寄付文化の広がり
- 「食」で人と人をつなぐ温かい心
という大切なメッセージ。
9月25日「10円カレーの日」は、食べることを通じて社会貢献や支え合いの精神を再確認できる記念日です。
次に日比谷公園を訪れる機会があれば、ぜひ松本楼のカレーを思い出してみてください。
その一皿には、半世紀以上続く“感謝と善意の物語”が込められています。
「今日の“今日は何の日”は秋分の日でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」
ABOUT ME
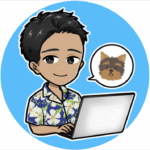
🌟一度きりの人生。周りを気にしすぎず、「自分の人生を生きよう」という思いを込めて。
お金・健康・グルメについて発信しながら、好きな時に好きな人とワイワイできる人生を応援します。
📌 経歴と活動
法人経営・不動産賃貸業(都内)
投資歴27年:高配当株・投資信託・iDeCo・NISA
大家歴20年:堅実な資産形成を実践
接客業歴30年:人とのつながりを大切に
🎯 モットー
『人は人、己は己』——比べる必要なし
『自分にしか決められない目標』を大切に
💡 興味・テーマ
資産運用(高配当株・投資信託・iDeCo・NISA)
健康・グルメ・ライフスタイルの質向上
「みんなでリッチに、健康に、幸せに」
🎉 趣味:麻雀・サウナ・料理・読書
特技:超絶旨いカレー作り
大切な時間:仲間とワイワイ・愛犬と過ごす時間
好きな食べ物:お鮨・お肉・お好み焼き
旅行スタイル:温泉宿でまったりと
🌈 メッセージ
「行動するか、しないか」——その小さな一歩が未来を大きく変えます。
一緒に明るい未来へ歩み始めましょう!
就職氷河期世代でも、行動すればなんとかなる✊
☆ 丸くなるな、星になれ