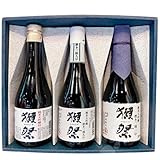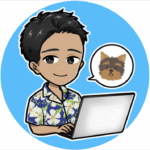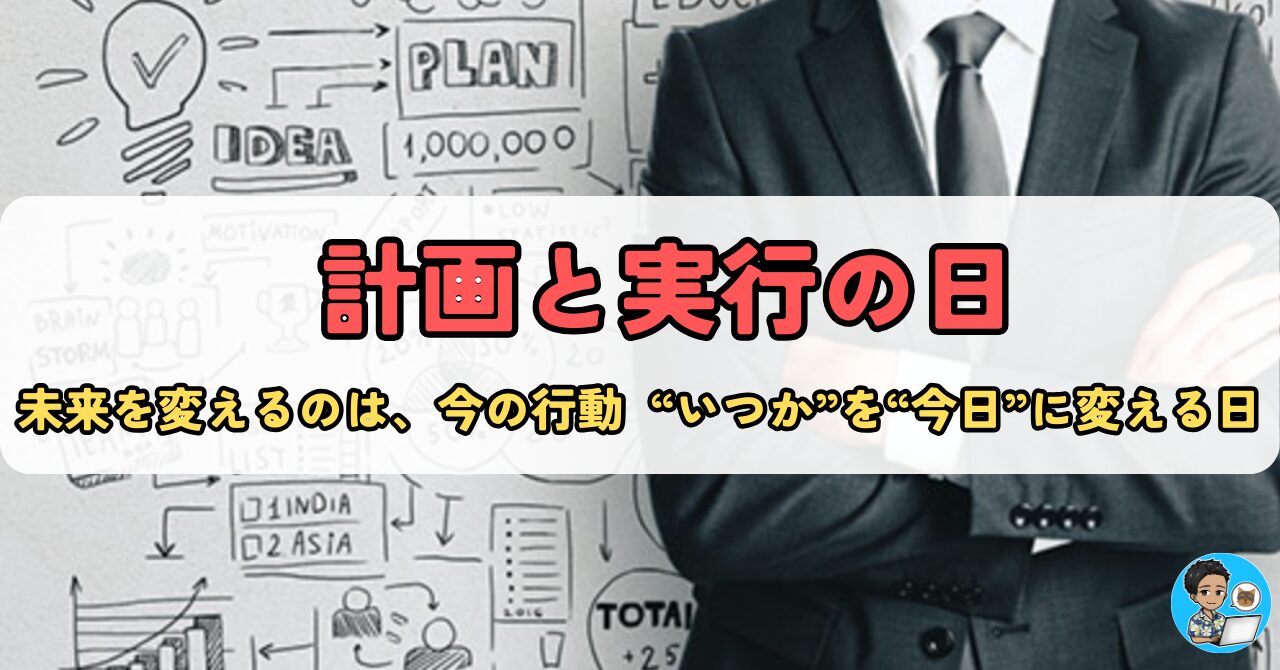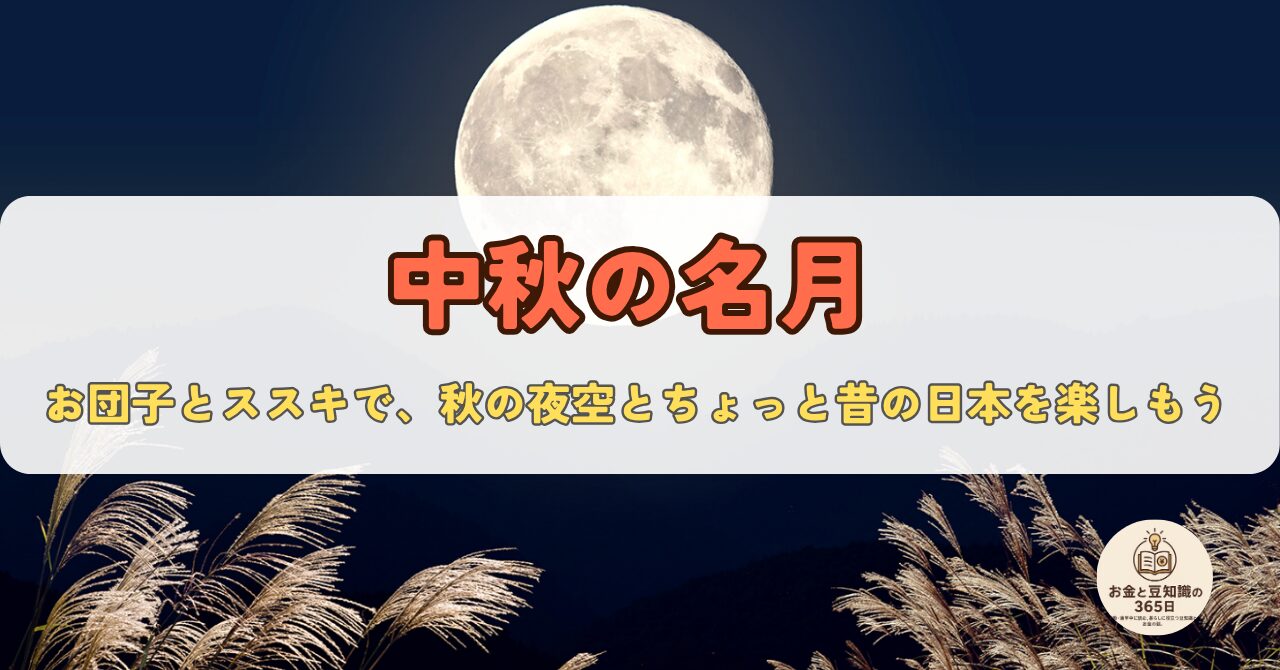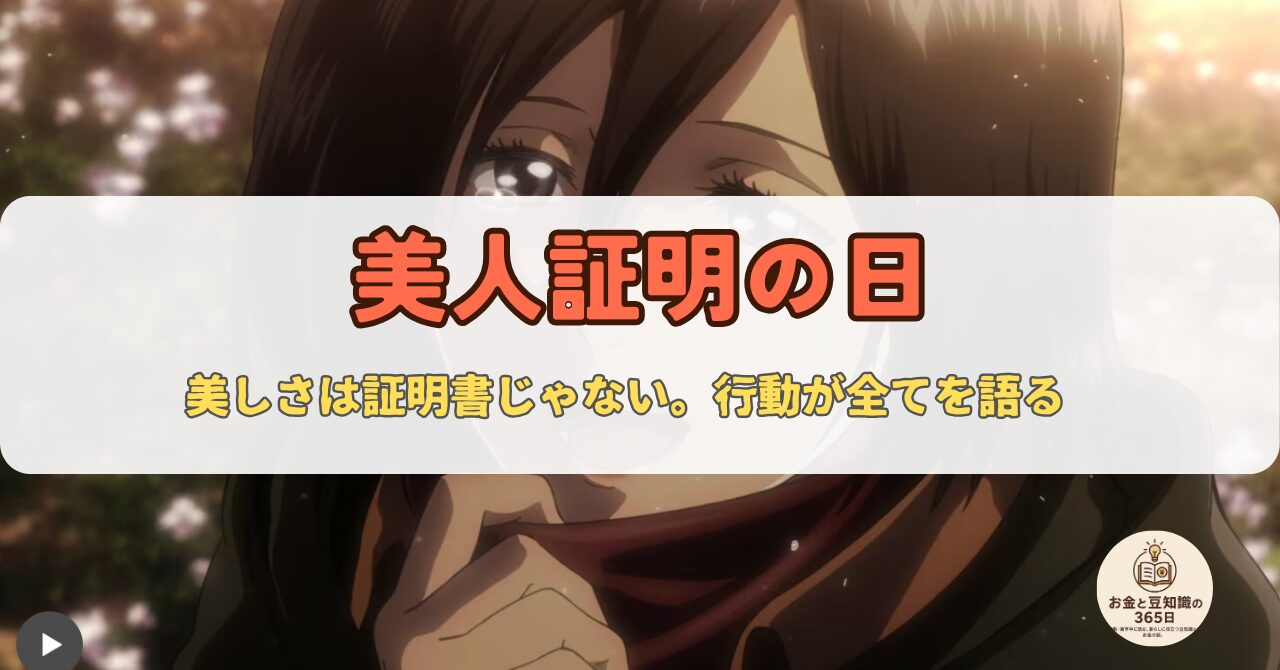10月1日【日本酒の日】日本の秋は日本酒で乾杯。伝統を味わい、未来へつなぐ一杯を

ふうぱー
こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日10月1日は、「日本酒の日」です。
ひやおろし、新酒、熱燗――秋は日本酒が一段とおいしく感じられる季節。
今日は、日本の伝統的なお酒「日本酒」を味わいながら、その文化や歴史に思いをはせてみませんか?

由来と制定の背景
- 「日本酒の日」は日本酒造組合中央会が1978年に制定。
- 日付の由来は2つ:
- 酒造年度の始まりが10月1日であること。昔から日本酒の造りは秋にスタートします。
- 十二支で“酉(とり)”が酒壺を表すとされ、10月は酉の月にあたること。
- 日本記念日協会にも登録され、業界・飲食店・酒蔵がこの日に合わせたイベントを展開しています。
日本酒の日に合わせた取り組み
1. 全国一斉「日本酒で乾杯!」イベント
- 日本酒造組合中央会が毎年10月1日に開催するキャンペーン。
- 全国各地の酒蔵・飲食店・百貨店・オンラインイベントで同時刻に乾杯する企画が行われる。
- SNSでは #日本酒の日 や #日本酒で乾杯 がトレンド入りすることも。
2. 酒蔵ツーリズムの拡大
- 10月は新酒造りのスタートシーズン。酒蔵見学や試飲ツアーが盛り上がる。
- 地域振興の一環として、酒蔵と観光をセットにした「酒蔵ツーリズム」が人気。
3. 新しい日本酒の楽しみ方の提案
- スパークリング日本酒、低アルコール酒、缶入り日本酒など、ライト層向けの商品が登場。
- フードペアリングの提案が多様化し、和食以外の料理(チーズ・チョコ・イタリアン)との組み合わせが人気。
4. 海外市場向けプロモーション
- 日本酒造組合や国税庁が中心となり、海外でのテイスティングイベント・日本酒アワードを開催。
- 各蔵元もオンラインショップや多言語ラベルを整備し、世界展開を強化。
5. 環境・サステナブルへの取り組み
- 酒米の安定供給・減農薬化、酒蔵でのCO₂削減、再生可能エネルギー利用などが進む。
- 一部蔵元では「酒粕のアップサイクル」や「エコボトル導入」も注目。
今後の課題と方向性
- 国内需要の再活性化:若い世代向けの商品開発や、SNS発信の強化がカギ。
- 酒蔵の事業承継問題:杜氏や蔵元の高齢化が進み、後継者育成が急務。
- 輸出依存リスク:海外人気に頼りすぎず、安定的な市場づくりが必要。
- 多様な嗜好対応:低アルコール・ノンアル・グルテンフリーなど新しい選択肢を拡大。
日本酒の日は、ただ乾杯するだけでなく、日本酒の未来を考えるきっかけでもあります。
国内消費減少と輸出拡大、若い世代の嗜好変化、サステナブルな酒造り――いま業界は大きな転換点に立っています。
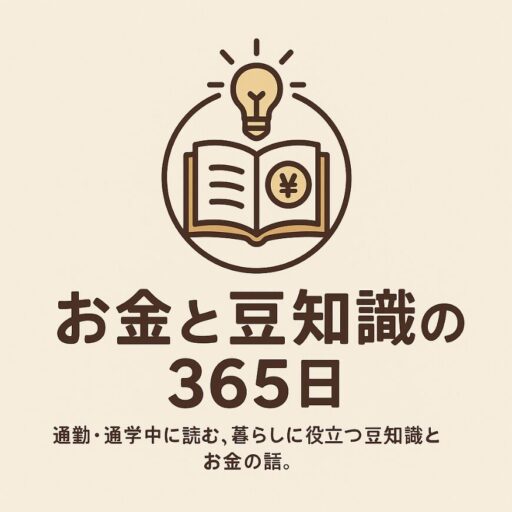
豆知識
誰かに話したい雑学
1. 日本酒は「米・水・麹」だけでできている
- 主原料はたった3つ。添加物は使わず、米を発酵させてアルコールを生む世界でも珍しい製法です。
- 麹菌(日本の国菌)が米を糖化し、酵母がアルコールに変える“並行複発酵”は日本酒ならでは。
2. 酒造りの新年は10月1日から
- 日本酒の世界では10月1日から翌年9月30日までを「酒造年度(BY:Brewery Year)」と呼ぶ。
- 新米の収穫が始まり、冬にかけて酒造りが本格化するためこの日を年度初めに設定。
3. 十二支の「酉(とり)」は酒壺の象徴
- 10月は十二支で「酉の月」。酉の字は“酒を入れる壺”の形から生まれたといわれ、日本酒との結びつきが深い。
4. 日本酒は“冷や”が常温を指す
- 「冷や酒」と聞くと冷たい酒を思い浮かべるが、元々は常温の酒のこと。
- 冷蔵技術がなかった時代の言葉が今も残っています。
5. 精米歩合が味を決める
- 米を削る割合=精米歩合。削るほど雑味が減り、香りと繊細さが際立つ。
- 大吟醸は精米歩合50%以下、純米大吟醸は米と水と麹のみで作られます。
6. 日本酒の種類は「特定名称酒」と「普通酒」に大別
- 純米酒・吟醸酒・大吟醸などは「特定名称酒」。
- 価格の約7割を占めるのは、実は「普通酒」と呼ばれるカテゴリです。
7. 日本酒は世界で“プレミアムSake”として人気上昇中
- 海外では純米大吟醸やスパークリングSAKEが高級酒として人気。
- 特にフランスの三つ星レストランで日本酒が提供されるなど、ワインと並ぶ地位を確立しつつあります。
8. 日本酒は温度で名前が変わる
- 熱燗(50℃前後)、ぬる燗(40℃台)、人肌燗(35℃前後)、冷や(常温)、花冷え(10℃前後)、雪冷え(5℃前後)など。
- 温度による呼び名の豊かさは世界でも珍しい文化です。
9. 酒蔵は全国に約1100軒
- 昭和40年代には約3000軒あった酒蔵が、現在は1/3ほどに減少。
- 小規模蔵が個性ある酒造りで人気を集めているのが最近のトレンド。
10. 日本酒は和食以外とも相性抜群
- チーズやチョコレート、フレンチ、イタリアンともマリアージュできる。
- アミノ酸が豊富なため、旨味の強い料理と特に相性が良い。
まとめ
「日本酒の日」は、日本酒造りの新しい年度の始まり(10月1日)と、十二支の“酉=酒壺”にちなむ日として1978年に制定されました。
長い歴史を持つ日本酒文化を未来へつなぎ、造り手の技と伝統をたたえる日でもあります。
日本酒の国内消費は減少していますが、海外では“SAKE”として高級酒の地位を確立しつつあり、輸出は過去最高を更新中。
一方で、蔵元の減少や後継者不足、気候変動・原材料確保といった課題もあります。
今日10月1日は、
- 日本酒の造りの始まりを祝って乾杯し、
- 「冷や=常温」「酉=酒壺」などの雑学を楽しみ、
- 日本の伝統文化の奥深さを感じる日。
日本酒の日は、伝統を味わい、未来を考えながら一杯を楽しむ日。
今日の乾杯は、少し特別な気持ちで味わってみませんか?🍶✨
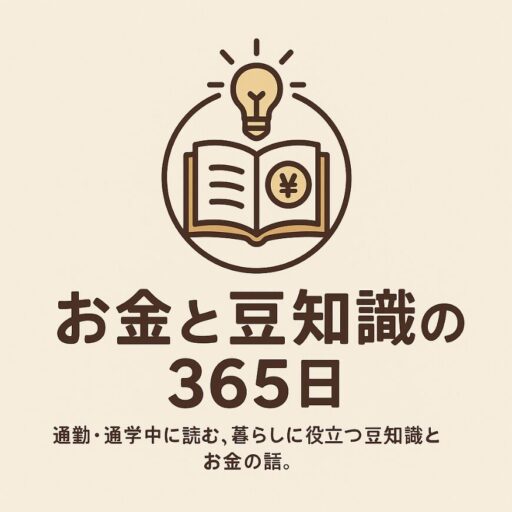
「今日の“今日は何の日”は「日本酒の日」でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」
広告
ABOUT ME