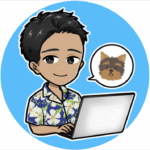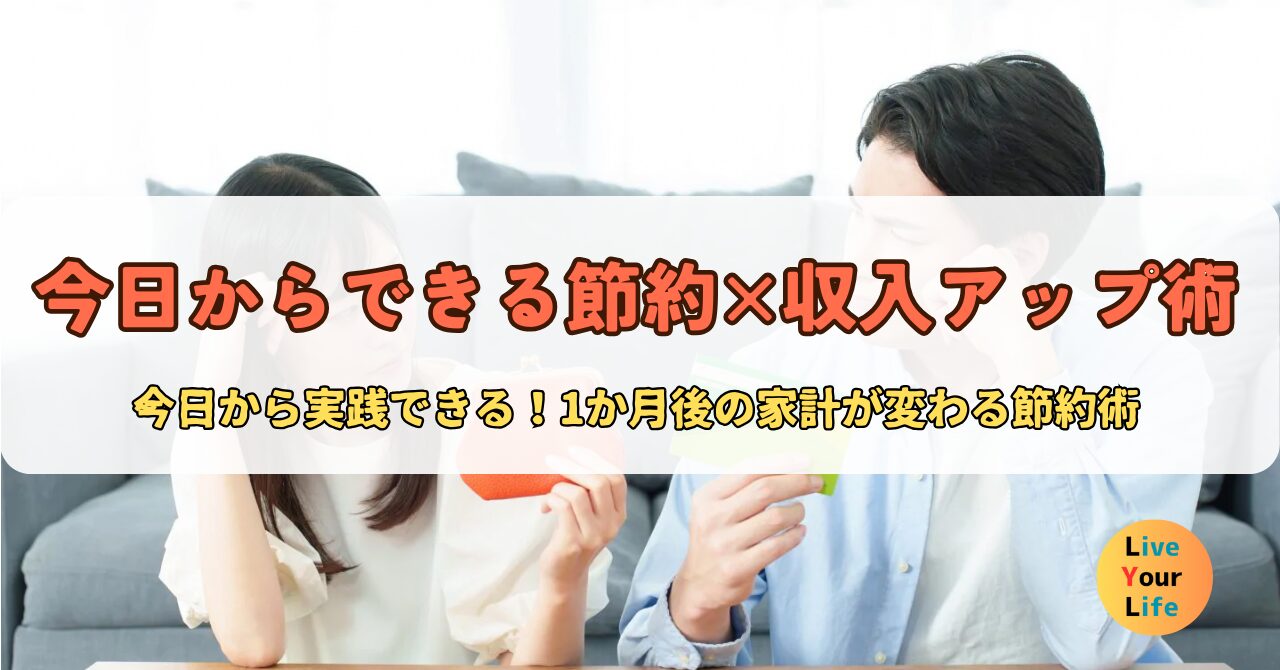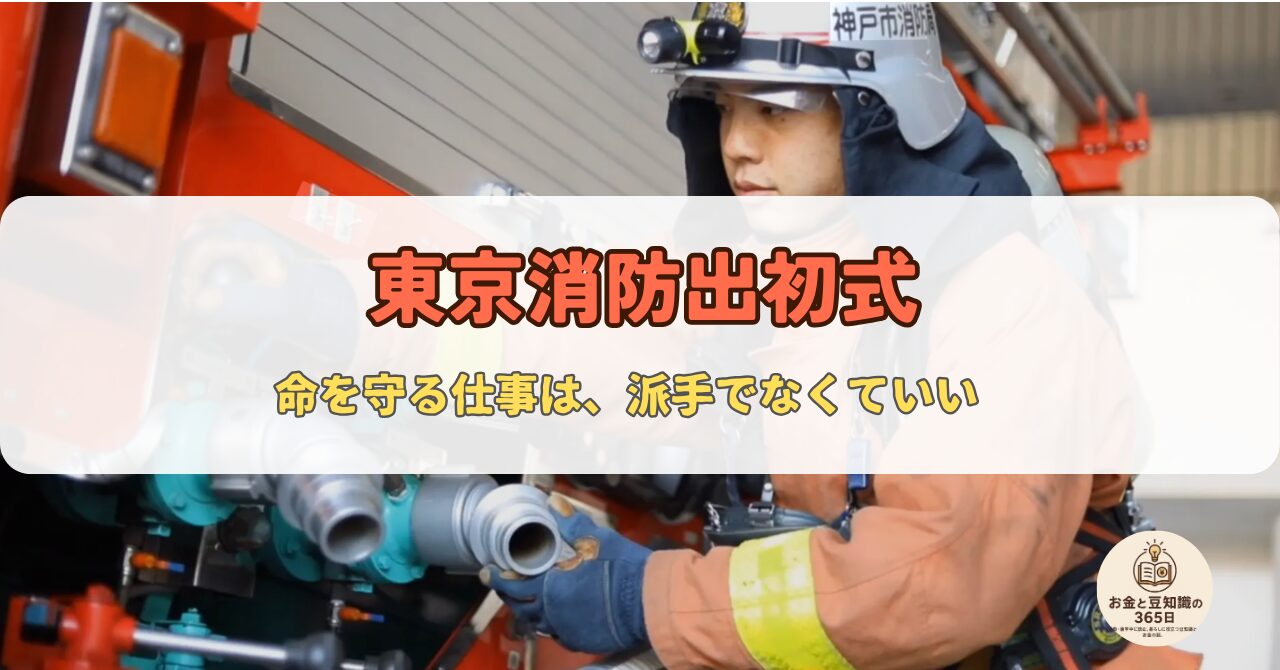厚生年金とは?しくみ・使いどころ・メリット&デメリットを徹底解説!
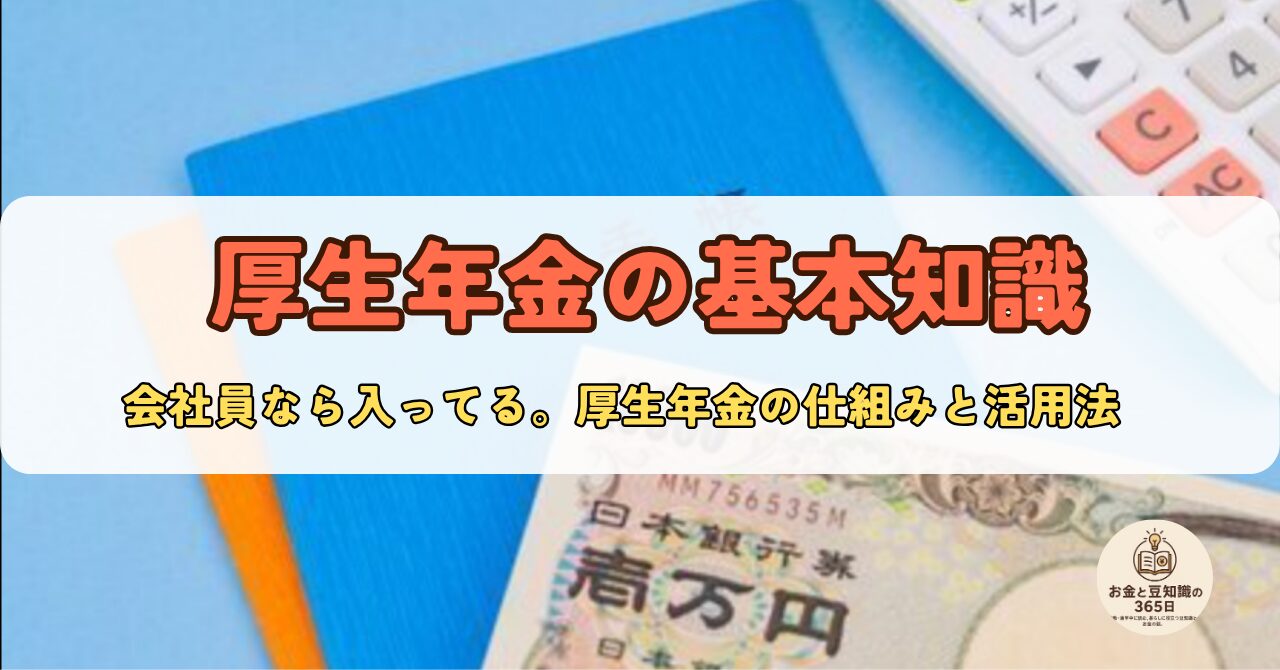
こんにちは。
毎日お仕事お疲れ様です。
毎月楽しみな給料日、給与明細に記載されているあれこれ、学んで納得して働きたいですね。
「厚生年金って毎月けっこう引かれてるけど、これって本当に必要?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
この記事では、会社員や公務員などが加入する「厚生年金保険」について、
その仕組みや使い道、メリット・デメリットをやさしく解説します。
厚生年金とは?
厚生年金保険(こうせいねんきん)は、会社員や公務員などの働く人が加入する年金制度です。
すべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」に、上乗せする形で支給されるため、将来もらえる年金額が多くなります。
加入するのはどんな人?
- 会社に勤める 正社員・契約社員・派遣社員
- 一定の条件を満たす パート・アルバイト(週20時間以上・月収8.8万円以上など)
- 公務員
入社すると会社が自動的に手続きをしてくれるので、自分で申し込む必要はありません。
どうやって保険料を払うの?
- 保険料は 毎月の給料とボーナスに比例
- 保険料率(2025年時点):約18.3%
- このうち、会社が半分を負担してくれる(つまり9.15%分は会社が支払う)
- あなたの負担分は、給料から自動的に天引き
たとえば月給30万円の人なら、約27,000円前後が厚生年金として差し引かれます(実際には会社が同額を負担)。
どれくらい加入すればもらえるの?
- 原則として10年以上加入すれば、老後に年金を受け取れる資格が得られます。
- 加入期間が長く、収入が多いほど、将来の年金額も増えます。
厚生年金が使える場面
1. 老後の生活費に(老齢厚生年金)
65歳になると、老齢年金が支給されます。
厚生年金に加入していた人は、国民年金(老齢基礎年金)に加えて「老齢厚生年金」が上乗せされて支給されます。
- 支給開始:原則65歳〜(希望すれば繰上げ・繰下げも可能)
- 金額:加入期間と収入の平均に応じて増える
- 長く働いた人・高収入だった人ほど、受取額も多くなる
💬 例)30年間加入・年収500万円前後なら、月額10万円以上の厚生年金を受け取れる場合も。
2. 障害を負ったとき(障害厚生年金)
病気やケガで、日常生活や仕事に大きな支障が出たときに支給されます。
- 対象:初診日が厚生年金加入中であること
- 等級:1級〜3級まであり、重症度に応じて支給額が変わる
- 特徴:3級でも支給対象(国民年金では2級以上のみ)
💬 例)うつ病、がんの後遺症、交通事故なども対象になることがあります。
仕事を続けるのが困難な場合でも、一定の生活費をカバーできます。
3. 家族のために(遺族厚生年金)
もしも本人が亡くなったとき、遺された配偶者や子どもに支給される年金です。
- 対象:配偶者(特に妻)・子ども(18歳未満)・父母など
- 条件:亡くなった人が厚生年金に一定期間加入していたこと
- 金額:亡くなった人がもらえたはずの厚生年金の約3/4が支給される
💬 例)小さな子どもを育てている家庭や、専業主婦の家庭にとっては非常に重要な支えになります。
💡 ポイントまとめ
厚生年金は、「老後の備え」だけではなく、
- 病気や障害で働けなくなったとき
- 家族を支える立場で亡くなってしまったとき
といった、人生のさまざまなリスクにも対応している制度です。
以下にまとめると、
厚生年金のメリット
① 将来もらえる年金額が多い
厚生年金は、国民年金(基礎年金)に上乗せされる仕組みです。
- 加入期間と収入が多いほど、将来の受取額が増える
- 会社員として40年間働いた人は、月10万円〜15万円程度の年金を受け取るケースも
💡 国民年金だけだと年額78万円(月6.5万円)程度なので、老後の安心感が大きく違います。
② 保険料の半分を会社が負担してくれる
毎月の保険料は約18.3%(2025年時点)ですが、その半分を会社が支払うため、個人の負担は実質半分で済みます。
💬 自営業者は国民年金を全額自己負担なので、同じ社会保障を受ける上で非常に有利です。
③ 障害や死亡時にも手厚い保障がある
- 障害厚生年金:等級3級から支給される(国民年金では2級以上のみ)
- 遺族厚生年金:配偶者や子どもに年金が支払われる
💡 万が一のとき、自分だけでなく家族も守れるという安心感があります。
④ 働く期間が長いほどお得
定年を超えて働き続けることで、
- 年金受給を遅らせると年金額が最大42%増える
- 将来もらえる金額を計画的に増やせる
⑤ 税制上の優遇もある
厚生年金保険料は「社会保険料控除」の対象で、年末調整や確定申告で所得税が軽減されます。
厚生年金のデメリット
① 毎月の手取りが減る
- 保険料は給料から天引きされるため、手取り額が少なく感じる
- 特に20代や収入の少ない時期には、「負担が大きい」と感じやすい
② 自分で管理できない
- 加入・脱退などは会社が行うため、自分で自由にコントロールできない
- 退職・転職時には自動で変わるが、自営業になると国民年金への切り替えが必要
③ 年金制度の将来に不安を感じる人も
- 少子高齢化により「将来もらえないのでは?」という不安の声も
- ただし、国が制度を維持するための改革は続いており、完全になくなることはまず考えにくい
④ 途中での脱退が基本できない
- 加入中は原則として脱退できない
- 節約のために「辞めたい」と思っても、強制加入である点はデメリットと感じる人も
国民年金との違い
| 比較項目 | 厚生年金 | 国民年金 |
|---|---|---|
| 加入対象 | 会社員・公務員など | 自営業・フリーランスなど |
| 保険料 | 給料に比例/折半 | 月額16,980円(定額) |
| 年金額 | 高め(収入に比例) | 一律(満額で年約78万円) |
| 支払い方法 | 給料天引き | 自分で納付 |
| 保障内容 | 老後・障害・遺族+上乗せあり | 基本保障のみ |
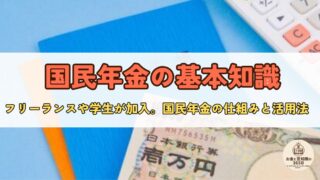
まとめ:厚生年金は「長期的な安心」のための制度
厚生年金は、短期的には「手取りが減る」などの負担感がありますが、
老後の生活費、万が一の病気・けが・死亡の備えとして、非常に優れた社会保障制度です。
若いうちはそのありがたみを感じにくいかもしれませんが、
「将来の自分と家族を守るための投資」と考えると、納得できる制度と言えるでしょう。
そして何より、自分の意思とは関係なく確実に引かれて積み立てられているという点で、
「将来への備えを“自動でしてくれている”」とも言えます。これは、実はとても心強い仕組みです。
無理な節約は続かないし、何より楽しくないのでNGです🙅
けど、適度な節約、家計管理は明るい未来を歩むためには必要。
自分にあったバランス見つけて、『節約と投資』程よい温度感で続けましょう。
今と未来のバランス、答えを持っているのはあなただけですから。