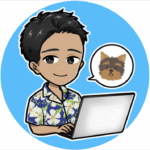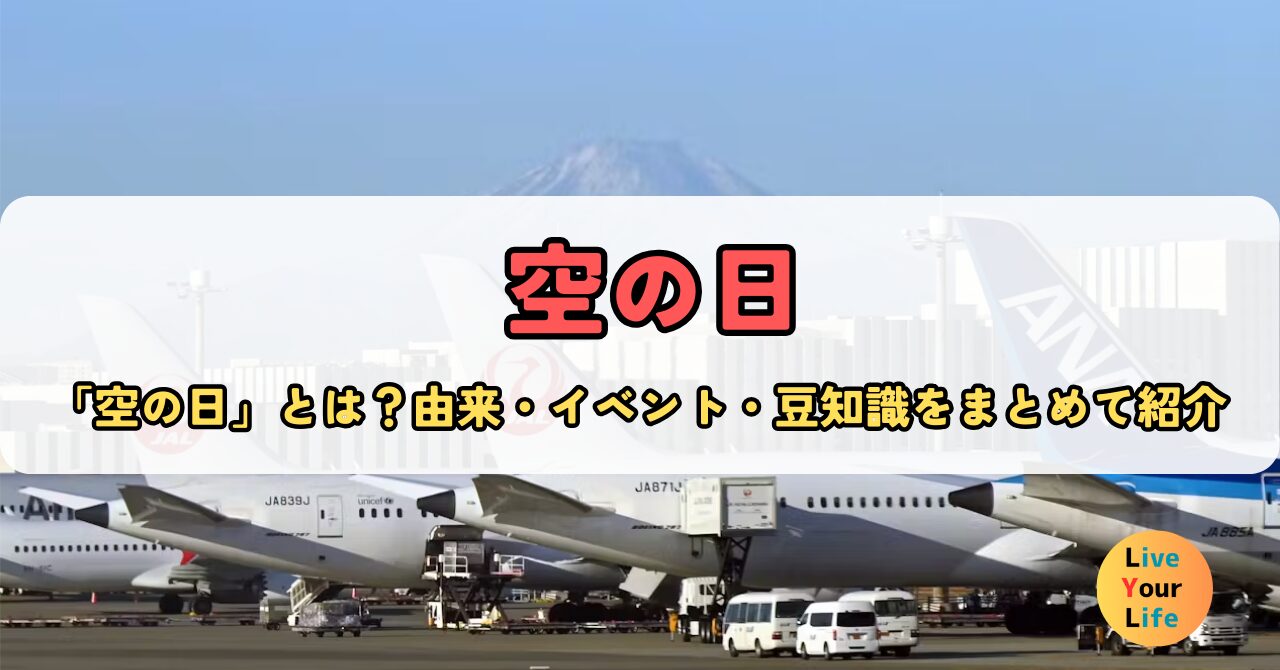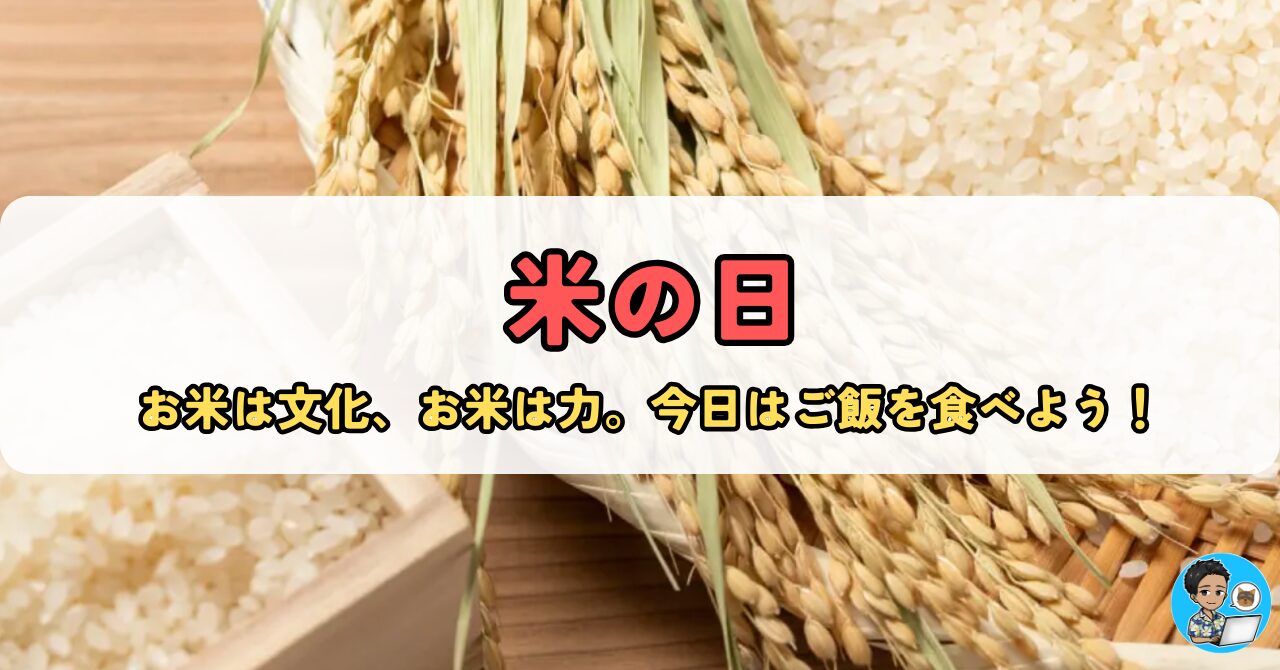10月16日【世界食料デー】食べることは、生きること。分け合うことは、未来をつくること

こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日10月16日は、「世界食料デー(World Food Day)」です。
毎日当たり前のように食べている食事。
でも、世界には飢えに苦しむ人が約7億人以上いるといわれています。
一方で、まだ食べられるのに捨てられている“食品ロス”は、
世界全体で年間13億トンにも上るという現実――。
そんな「食の不均衡」を見つめ直し、
“すべての人が食べられる世界”を目指すための日が、この「世界食料デー」なんです。
今日は、食べものへの“感謝”と“責任”を考える一日にしてみませんか?
世界食料デーとは?
国連が制定した「食の記念日」
「世界食料デー」は、国連食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization)が
創立された日(1945年10月16日)にちなんで制定されました。
FAOは、世界の飢餓・栄養不足・農業問題の解決を目指す国連機関で、
1981年に「世界食料デー」を公式に定め、
現在は150か国以上が参加する国際的な記念日となっています。
目的は「すべての人に、食べものを」
世界食料デーの目的はとてもシンプル。
「すべての人が、十分な食料を得られる世界をつくる」こと。
FAOはこの理念を掲げて、次の課題に取り組んでいます:
- 飢餓や栄養不良の撲滅
- 食料生産の安定化と農業支援
- 食品ロス・廃棄の削減
- 公平な食料分配と持続可能な農業
つまり、“食べものを分け合う日”であり、“考える日”でもあるんです。
現状と課題:世界と日本の「食のギャップ」
世界の現実:まだ7億人が飢えている
国連WFP(世界食糧計画)によると、
2024年時点で飢餓人口は世界の約9人に1人(約7億人)。
紛争、気候変動、経済格差によって、
特にアフリカや中東地域では慢性的な食料不足が続いています。
さらに、子どもの5人に1人が十分な栄養を摂取できていないという深刻なデータも。
日本の課題:食品ロスは年間約523万トン!
日本でも、まだ食べられるのに捨てられている食品――いわゆる「食品ロス」が大問題。
- 家庭から:年間約244万トン
- 事業者から:約279万トン
合計で年間523万トン(2022年度推計)、
これは世界の食料支援量の1.2倍にあたります。
つまり、「食料が足りない国がある一方で、
食料を捨てている国もある」という現実がここにあるのです。
キーワードは「もったいない」と「つながる」
“もったいない”という言葉は、
もともと「命や恵みを大切にする心」から生まれた日本語。
世界中で「MOTTAINAI」という言葉が使われるようになったのも、
“食を大切にする日本の文化”が共感を呼んだからです。
この精神をもう一度見直すことが、
「世界食料デー」の本当の意義につながります。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
① “世界食料デー”は150か国以上が参加!
FAO主導のこの活動には、世界中の国々が参加。
各国で「食の祭典」「チャリティマラソン」「フードドライブ」など、
地域ごとに特色あるイベントが行われています。
② “世界食料デー月間”がある!
日本では、10月を「世界食料デー月間」と位置づけ、
政府・NPO・企業・学校などが連携して、
食品ロス削減や募金キャンペーンを実施しています。
③ “飢餓ゼロ”を目指す「SDGs目標2」
SDGs(持続可能な開発目標)の**Goal 2「飢餓をゼロに」**は、
まさにこの「世界食料デー」の理念と一致。
国連は2030年までに飢餓を撲滅することを掲げています。
④ “フードドライブ”ってなに?
「フードドライブ」とは、家庭や企業で余っている未使用食品を集め、
食料に困っている人々へ届ける活動のこと。
日本でも各地のスーパーや自治体で実施されています。
⑤ 世界では「食べ残し禁止法」も!
フランスでは2016年に「食品廃棄禁止法」が施行され、
スーパーが売れ残りを廃棄することを禁止。
アメリカ・デンマークなども、フードバンク制度を整備しています。
“食べ物を最後まで使い切る社会”が、すでに世界の常識になりつつあるんです。
⑥ “飢餓”は栄養不足だけじゃない
FAOは「栄養の不均衡も“隠れた飢餓”」と定義しています。
つまり、“食べすぎ”や“偏った食事”も、
“栄養が届いていない”という意味では“飢餓”の一種なのです。
今日からできる「食料デーアクション」5選
1️⃣ 食べ残しを減らす(買いすぎ・作りすぎ防止)
2️⃣ フードドライブに寄付する
3️⃣ 地産地消の食品を選ぶ
4️⃣ 食材を最後まで使い切る「リメイク料理」
5️⃣ 家族で“食のありがたみ”を話してみる
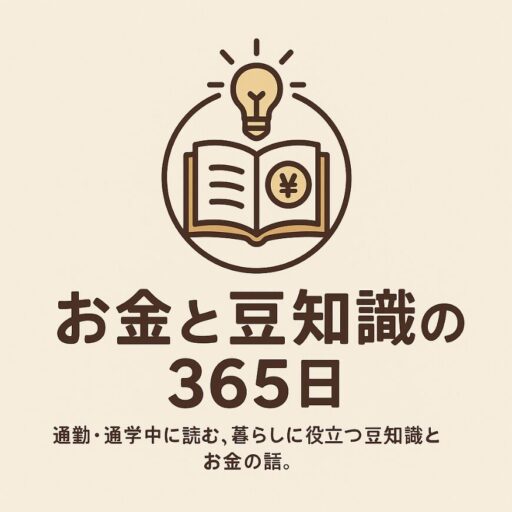
まとめ
― 食べものの重みを、もう一度見つめる日 ―
10月16日の「世界食料デー」は、
“食べものがあることのありがたさ”を世界規模で考える日です。
私たちは毎日何気なく食事をしていますが、
その一皿の裏には、
農家の人の努力、輸送に関わる人の手、自然の恵み、そして命の循環があります。
それを「当たり前」と思ってしまう現代だからこそ、
“食”を見直すことが求められています。
「満たされている私たち」にできること
飢えに苦しむ人は世界で約7億人。
一方で、日本では年間523万トンの食品ロスが出ている――
このコントラストこそが、世界が抱える“食の不均衡”です。
「世界食料デー」は、罪悪感を抱く日ではなく、
“できることを考える日”。
・買いすぎない、作りすぎない
・残さず食べる
・寄付やフードバンクに協力する
・感謝をこめて「いただきます」と言う
そんな小さな一歩が、確実に未来を変えていきます。
“食”は、命をつなぐ共通言語
人種も宗教も国も超えて、
“食べる”という行為は人類共通の営みです。
誰かの「おいしい」が、
別の誰かの「明日を生きる力」につながる。
“食べること”は、“分かち合うこと”でもあるのです。
そして、私たちが無駄なく感謝して食べる姿勢そのものが、
世界の飢餓を減らすための静かなメッセージになります。
一粒のごはんが教えてくれること
「一粒の米にも七人の神がいる」――そんな言葉があります。
それは、自然と人、そして命のリレーへの感謝の象徴。
おにぎり一つ、パン一枚にも、数えきれない人の手が関わっています。
その思いを感じ取ることができたら、
食べものの扱い方も、買い方も、きっと変わっていくはずです
結びのメッセージ
「世界食料デー」は、
“食の課題を知る日”ではなく、
“命のありがたみを味わう日”。
飢えをなくすのは、遠い国の問題ではなく、
今日の私たちの行動から始まる世界規模の挑戦です。
「今日の“今日は何の日”は「世界食料デー」でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」