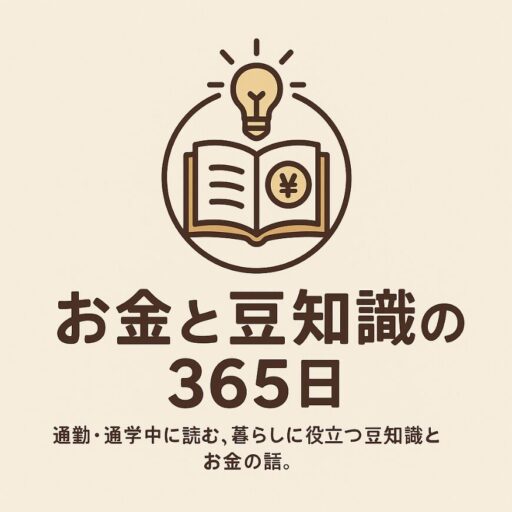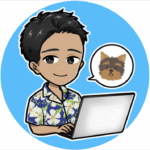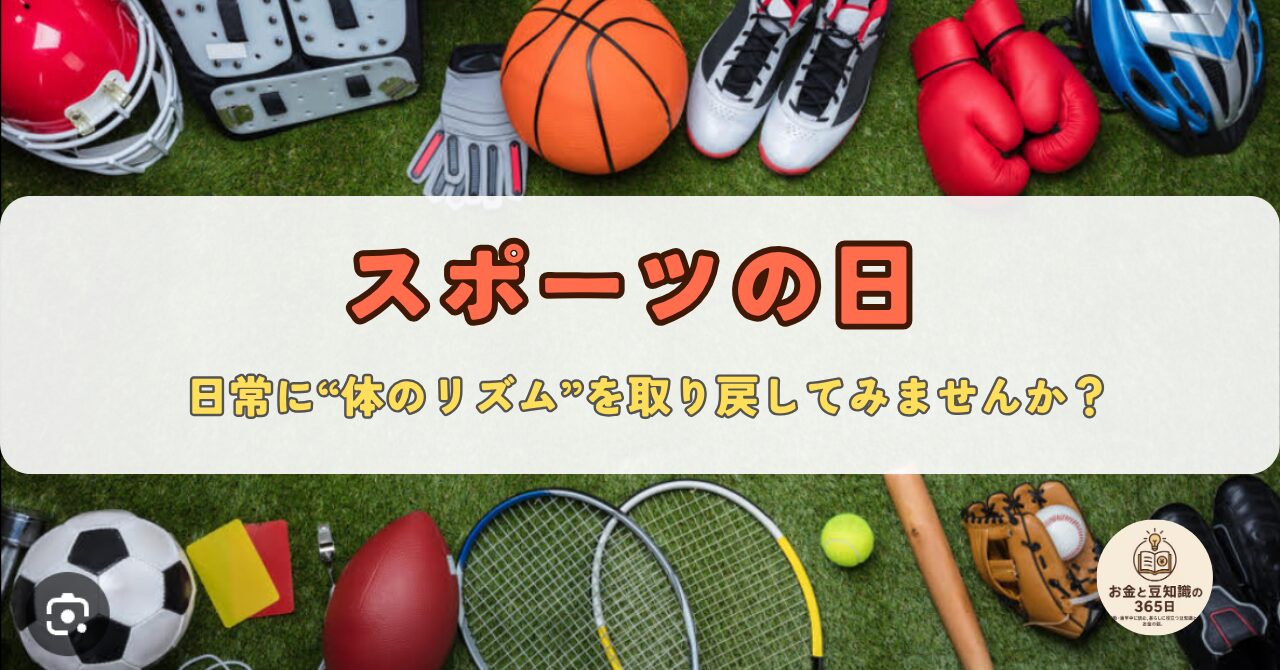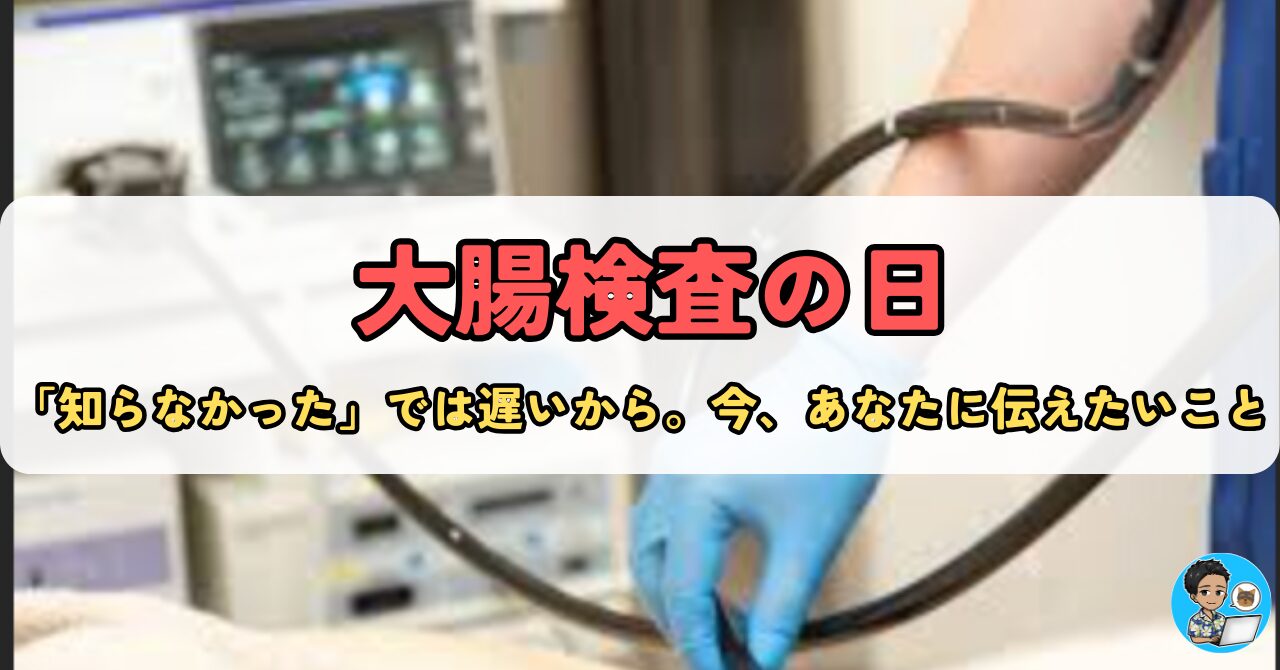9月9日【救急の日】救急車が来る前に、できることがある。救急の日に考える“いのちの備え”
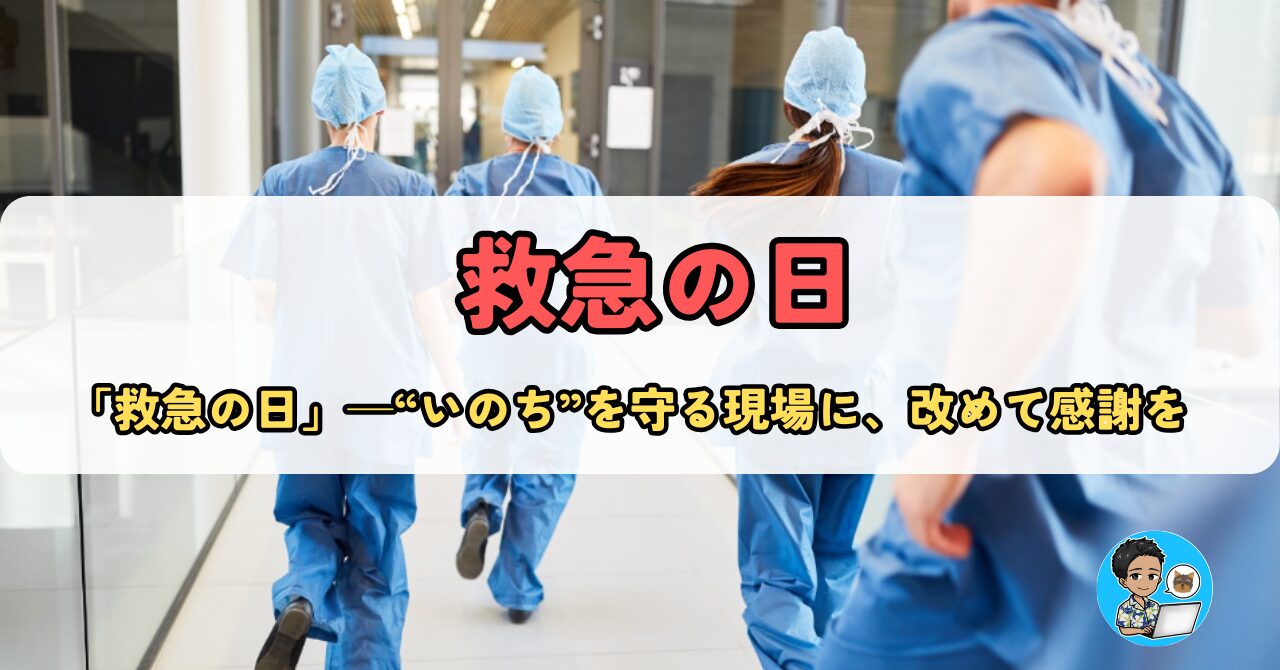
こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日9月9日は、「救急の日」です。
救急の日(9月9日)特集:命のリレーをつなぐということ
【歴史】なぜ「救急の日」が必要だったのか?
1982年、「救急の日」が制定された当時の日本は、
- 高度経済成長を経て都市化が急速に進み
- 交通事故・労働災害・高齢化による病気など、救急需要が激増していた時代
ところが、当時の社会は**「救急医療=特別な人の話」**という意識がまだ強く、
救急車の適正利用や、救急救命の知識はまだまだ一般に普及していませんでした。
その中で、政府はこう考えました:
「救急は、誰かに任せるものじゃなく、“自分にも関係のあること”として意識してもらおう」
この思いから、「救急の日」は始まったのです。
【現場のリアル】救急隊員は“人間ドラマ”の最前線にいる
救急車に乗る隊員たちは、ただ“運転して運ぶ”人ではありません。
- 救急救命士は、心肺停止患者に対して現場での医療処置が許されている数少ない職種
- 現場ではわずか数分で生死を分ける判断を求められることも
- 患者の家族の動揺、搬送先病院との連携…全てを一手に引き受けて動いている
🎥彼らの仕事は、ある意味「命のドキュメンタリー」。
時には、救えなかった命に胸を痛めながら、次の出動に向かうこともあります。
【私たちの課題】“救急車の無料”が抱えるジレンマ
実は、日本の救急車出動件数は年々増加傾向。
その背景には:
- 高齢化による救急依存
- 「救急車=無料タクシー」と誤認する人の存在
- すぐに病院に行きたいという不安心理
こうした“軽症での要請”が増えることで、本当に必要な人の元に救急車が間に合わないリスクが出てきます。
だからこそ、私たち一人ひとりが「本当に今、救急を呼ぶべきか?」を冷静に判断することが求められています。
【未来】救急医療はどう進化していくのか?
日本の救急医療は、これからも進化が期待されています:
- 📱スマホからの緊急位置情報通報(GPS対応)
- 👩⚕️AIによる「トリアージ(緊急度判定)」の導入
- 🚁ドクターヘリ・ドローン医療物資搬送の実用化
- 💊遠隔診療やAI診断との連携による**“搬送しない救急”**の時代へ
さらに、**「地域住民による応急処置の普及」**もカギ。
すでにAED講習やCPR(心肺蘇生法)訓練を受けた市民の数は年々増加しています。
日本の「救急医療」、実は世界でもトップレベル!
- 📞119番通報から平均9分以内に救急車が到着(世界的にも超早い)
- 🚑救急車は無料(※税金で運営)
- 👨⚕️全国どこでも24時間対応の救急体制が整備されている
こうした体制は、日々努力を続ける救急隊員・医療従事者・消防関係者によって支えられています。

【救急の日】豆知識セレクション
1. 119番通報、実はこんなに賢くなっている!豆知識:
現在の119番通報では、「住所がわからなくても」通報できる仕組みが導入されています。
📱スマートフォンからの通報で、GPS位置情報が自動送信されるシステムが一部地域でスタート。
これは「どこにいるのかわからない観光客」「パニックで説明できない高齢者」などを救う重要な仕組み。
🚨さらに最近では、AIが通報者の声の震えから“緊急性の高い通報”を見極める研究も進行中です。
2. 日本の救急車は、実は“世界でも珍しい存在”
日本の救急車は、無料で利用できる数少ない国のひとつです(税金で運営)。
他の国では…
| 国名 | 救急車の料金(平均) |
|---|---|
| アメリカ | 5万円〜20万円(保険対象外も) |
| ドイツ | 約2万円(保険対象) |
| 韓国 | 緊急時無料、それ以外は有料 |
つまり、日本の救急車は**「世界でもっとも優しい救急システムのひとつ」**なのです。
🧭ただし、その結果「軽症での要請」が多発しているのも事実…
3. AEDの正式名称、言える💬豆知識:
AEDは、正式には…
Automated External Defibrillator(自動体外式除細動器)
✅「心臓がけいれんしている状態」を電気ショックでリセットする装置
✅ 実は、音声ガイド付きで誰でも使える!(触るのが怖い…と思ってる人が多い)
📌心停止から1分遅れるごとに救命率は約10%ずつ下がる。
📦だから「救急車を待つ」だけじゃなく、「その場にいる人の行動」が生死を分けることも。
4. 119番は“いつから”始まった?豆知識:
日本で119番が導入されたのは1948年(昭和23年)東京・大森消防署が初。
当時はまだ電話も普及していない時代。
それでも、「火事や急病に素早く対応するには“番号を統一すべき”」というアイデアから生まれました。
なぜ「119」か?という説には…
- ダイヤル式電話で回しやすいから(当時の1は最速)
- 「911」はアメリカと重なるから避けた
など、諸説あり。
5. 子どもが「救急車呼ぶ」練習って、意味あるの?豆知識:
はい、ものすごく大事です!
幼稚園〜小学校低学年でも、以下のような練習ができます:
- 📞 119番にかけるふり(※通報にはならないよう注意)
- 🗣「どこで・なにが・どうした」を伝える練習
- 🧸 人形を使ってAEDや胸骨圧迫のごっこ遊び
🎓実際に「小学1年生が母の命を救った」などの事例も報告されており、
**「子どもがヒーローになる現実」**は存在します。
救急の知識は、“今は使わないかもしれないけど、絶対にムダじゃない”
救急の話って、「自分には関係ない」って思いがちですが――
実は、「自分が助けられる側」になるよりも、「誰かを助ける側」になるチャンスのほうが多いんです。
1回の豆知識が、1人の命を救う「きっかけ」になるかもしれません。
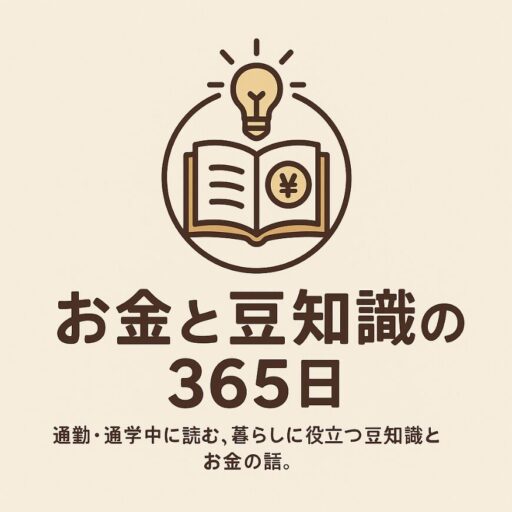

まとめ:私たちができる“救急”の備えとは?
① 家の中の「救急環境」を整える
具体的にできること:
- 救急箱の中身を見直す(使用期限・不足分)
- ばんそうこう、消毒液、包帯、常備薬、体温計など
- 家族全員の“持病・薬・アレルギー情報”を共有・記録
- ノートでもスマホメモでもOK。救急搬送時に超重要!
- 「緊急連絡先リスト」を家の見える場所に掲示
- 自宅電話が使えないことも想定して、紙で残すのがベター
🧠【深掘りPOINT】
救急箱は“薬の棚”ではなく、**「もしもの時に“動ける自分”を作る装備」**です。
② スマホを“命を守るツール”にする
今すぐできること:
- スマホの「緊急情報(メディカルID)」を設定
- AEDマップアプリをダウンロード(例:日本AED財団のアプリ)
- LINEや家族グループで「緊急時テンプレ」を共有(例:◯◯が倒れたら119、保険証とお薬手帳を一緒に)
💡おすすめアプリ例:
| アプリ名 | 主な機能 |
|---|---|
| MySOS | 医療情報の記録・救急支援アプリ |
| 救命ナビ | AEDの使い方や心肺蘇生法の解説 |
| 全国AEDマップ | 近くのAED設置場所が地図でわかる |
🧠【深掘りPOINT】
スマホは「連絡手段」だけじゃない。正しく設定すれば“ポケットの救急箱”になります。
③ 家族・身近な人と“もしも”の会話をしておく
話しておくべきこと:
- 「◯◯が倒れたら、誰が119する?」「病院はどこにする?」
- 「この薬は誰が管理してる?」
- 「おばあちゃん、AED使える?」←これ大事!
📌災害時も共通ですが、「いざという時に“言葉にしないと伝わらない”こと」って多いんです。
🧠【深掘りPOINT】
“命の情報共有”は、家族の安心を守る「もうひとつのセーフティネット」。
④ 市民向けの「救命講習」に参加する
やってみたいこと:
- 消防署主催の普通救命講習(約3時間)
- 企業や自治体のAED体験イベント
- オンライン講習(最近ではZoom対応も)
🧠【深掘りPOINT】
心肺停止が起きてから1分で救命率90%→5分後には50%以下。
「その場にいた人」が心肺蘇生(CPR)できるかどうかで命が決まる現実があります。
⑤ 心の備え:「人を助ける」って、勇気がいります
「私なんかが救命してもいいのかな…?」
「もし失敗したらどうしよう…」
こんな不安は、誰にでもあります。でも、
⏱何もしなければ、命は失われるかもしれない
⏱手を差し伸べれば、助かる可能性が生まれる
救命講習でも教わりますが、**“迷っている時間が最も危険”**なんです。
🧠【深掘りPOINT】
あなたの「一歩踏み出す勇気」が、プロの医療チームにつなぐ“命のリレー”の最初のバトンになります。
備えとは、「知っておくこと」ではなく「動けること」
救急車を呼ぶだけでは救えない命もある。
だからこそ、「備えること」は“行動の準備”でもあります。
今日できること、ちょっとだけでも始めてみませんか?
- 家の救急箱を見直す
- スマホを救命仕様にする
- 家族と会話する
- 講習を調べてみる
どれも「1分でできる命の準備」です。