こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日10月5日は、「味噌おでんの日」です。
秋の訪れとともに恋しくなる、あたたかいおでん。
その中でも、赤味噌を使ったコク深いタレをかけた味噌おでんは、日本の食文化を代表する郷土の味のひとつ。
肌寒い日に湯気を立てる味噌おでんを食べれば、体だけでなく心までほっと温まります。
今日はそんな「味噌おでん」に注目し、歴史や魅力、食文化の背景を少しのぞいてみましょう。
だれが作った記念日?
- 制定者は、群馬県甘楽町の株式会社ヨコオデイリーフーズ(「こんにゃくパーク」運営)。自社の人気商品「月のうさぎ 田楽みそおでん」のPRと市場活性化を目的に記念日化しました。
なぜ10月5日なの?
- 1994年10月5日に、同社が「田楽おでんにみそだれを付けて」発売したことが起点。発売“記念日”をそのまま記念日にした、商品由来型の設定です。
公式な認定は?
- 2016年に日本記念日協会が認定・登録。協会の紹介記事や当時のプレスリリースでも登録経緯が確認できます。
どんな狙い・メッセージ?
- こんにゃく・味噌おでんの需要期(秋口)に合わせ、家庭でも気軽に味噌おでんを楽しむきっかけづくりと、こんにゃくの消費拡大・市場活性化を掲げています。
現状と取り組み
- 愛知県や岐阜・三重の飲食店では、10月5日前後に味噌おでんのフェアやイベントを開催。
- スーパーやコンビニもこの時期に合わせて「味噌おでん」仕様の商品を展開。
- 観光PRとして、ご当地おでんマップや味噌おでん食べ歩きイベントが実施されることもあります。
- 全国的にも赤味噌文化を広めるため、SNSキャンペーンやレシピ紹介が活発に行われています。
味噌おでんの日が持つ意味
1. 郷土料理としての「再発見」と継承
- 味噌おでんは愛知県・三河地方を中心に根付く赤味噌文化の象徴。
- 八丁味噌などをベースにした甘辛い味噌だれは、各家庭や地域で味が異なり、“おふくろの味”の一つとも言われています。
- 記念日をきっかけに、家庭での手づくりレシピや地元の味の再評価が進むことが期待されています。
2. 地域発ブランドのPR・観光活性化
- 「味噌おでんの日」を中心に、イベントやフェアが実施されることで観光資源化が進む。
- こんにゃくや味噌の地元メーカーにとっても、秋冬の需要喚起・商品ブランディングの絶好の機会になっています。
- 地元の食文化をPRすることで、地域経済の活性化や名産品のブランド価値向上につながっています。
3. 家庭の食卓を豊かにするきっかけ
- 忙しい現代でも簡単に作れる家庭用の味噌おでんセットやレトルト製品の普及を後押し。
- 「外食だけでなく、家庭でも簡単に楽しめる郷土グルメ」として新しい価値を提案しています。
- 子どもや若い世代が味噌文化に親しむ入り口にもなりやすいです。
4. 日本の“味噌文化”の再評価
- 味噌消費量は戦後から徐々に減少しており、若い世代では味噌離れが進行。
- 記念日を通じて味噌の栄養価(発酵食品・腸活効果・イソフラボンなど)や健康メリットを発信できる機会にもなっています。
味噌おでん文化の課題
1. 若年層への食文化継承
- 家庭で味噌を使った料理が減少しており、“味噌だれおでん”を知らない若い世代が増加。
- 記念日を活かしたSNS発信や動画レシピなど、若者向けアプローチの工夫が課題です。
2. 地域差による認知の壁
- 「味噌おでん=名古屋」とのイメージが強く、他地域の独自味噌おでん文化が埋もれている。
- 全国的な広がりや多様な味の発信が今後のテーマになります。
3. 健康志向との両立
- 味噌は塩分が多いため、塩分摂取量を気にする消費者への配慮が求められる。
- 減塩や発酵の健康効果をどう発信するかが重要。
4. 食材・製造業界の持続可能性
- 味噌製造業界は職人不足や後継者問題を抱えており、地域ブランドの存続が課題。
- 記念日を通じて産地・メーカーの価値を伝える取り組みが求められています。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
誰かに話したい雑学
1. 味噌おでんのルーツは「田楽」から
- 江戸時代、豆腐やこんにゃくに味噌を塗って焼く田楽料理が発展。
- これが後に煮込み料理と融合して、こんにゃくや大根を味噌で煮込む味噌おでんスタイルに進化しました。
2. 八丁味噌は400年以上の歴史を持つ
- 八丁味噌は愛知県岡崎市の八帖町(八丁村)で江戸時代から作られている赤味噌。
- 木桶で2年以上発酵熟成させるため、コクと旨みが深く、味噌おでんの味を決める重要な存在です。
3. 名古屋式「串おでん」が独特
- 名古屋の屋台では、大根やこんにゃく、玉子などを串に刺し、濃厚な赤味噌だれをたっぷりかけるのが定番。
- 醤油ベースの関東おでんと比べると、味が濃い・甘辛い・煮込み時間が長いのが特徴です。
4. 静岡おでんも味噌と関係が深い
- 黒はんぺんを使った静岡おでんは、ダシ粉(いわし・かつお節粉)をかけるほか、味噌だれを添えるお店も多い。
- 実は中部〜静岡一帯で味噌文化とおでんが密接につながっているんです。
5. 「味噌おでんの日」はこんにゃく文化ともリンク
- 記念日を制定したヨコオデイリーフーズはこんにゃくメーカー。
- こんにゃくは味噌との相性が抜群で、ヘルシーかつ味が染みやすい代表具材です。
6. おでんは地域ごとに名前が違う?
- 関東では「おでん」ですが、関西では昔「関東煮(かんとだき)」と呼ばれることも。
- 名古屋では「みそおでん」、青森では「しょっつるおでん」など、地域によって呼び方・味付けがバラエティ豊か。
7. 味噌は実は“発酵の力”で健康食
- 赤味噌にはメラノイジンという抗酸化成分や、腸内環境を整える善玉菌が含まれています。
- 塩分が気になるイメージがある一方で、適度な摂取は腸活・抗酸化・免疫サポートにも役立つと注目されています。
8. 日本の味噌消費量は減少傾向
- 1960年代には年間12kg以上だった味噌の一人当たり消費量が、いまは約4〜5kg程度に減少。
- 味噌おでんや味噌煮込み料理のPRは、味噌文化を守る動きの一環でもあります。
9. コンビニおでんも地域で味が違う
- セブンイレブンなどのコンビニおでんは、中部・東海エリアでは赤味噌仕立てが販売されることも。
- 関東・関西では醤油だしがメインなので、旅行先で食べ比べると意外な違いが楽しめます。
10. 家庭用“味噌だれ”の進化
- 市販の味噌だれは、甘め・辛め・赤味噌100%・合わせ味噌などバリエーションが豊富。
- 最近はレンジ調理やレトルトおでんなど時短アイテムも増えて、家庭でも簡単にご当地気分が味わえます。
まとめ
本質:なぜ「味噌おでんの日」なのか
- 郷土の記憶をつなぐ日:赤味噌文化(八丁味噌など)と屋台・家庭の“串おでん”という暮らしの風景を、次世代へ受け渡す合図。
- 秋の食卓を豊かにする日:湯気×甘辛だれの幸福感は、家族の会話と季節感を呼び戻す。
- 地域産業を応援する日:味噌・こんにゃく・練り物――地元メーカーの技術と雇用を“おいしさ”で支える。
課題:何に向き合うべき?
- 若年層の“味噌離れ”:家庭調理の簡便化が進むほど、味噌文化の接点が薄れがち。
- 健康志向との折り合い:塩分配慮・適量設計・素材選びで“おいしさ×ヘルシー”を両立。
- 多様性の発信不足:名古屋一極ではなく、静岡・岐阜・三重など各地の味噌おでんを見える化。
今日からできる3ステップ
- 家で“自分の味”を作る
基本だれ比率の目安:赤味噌2・みりん2・砂糖1・だし1(お好みで生姜少々)。
- ヘルシーに寄せる
だれは“追いがけ”で量コントロール/具は大根・こんにゃく・卵・豆腐中心に。
- 地域を味わう
“産地表示の味噌”“地元こんにゃく”“ご当地おでん食べ比べ”で小さく地域貢献。
楽しみ方アイデア
- 二色おでん:半分はだし煮、半分は味噌だれで“Wテイスト”。
- 卓上トッピング:白ごま・一味・柚子皮・刻みねぎで香りを重ねる。
- SNS企画:#味噌おでんの日 で“我が家の比率”や“地元流”を共有。
「今日の“今日は何の日”は「みそおでんの日」でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」
ABOUT ME
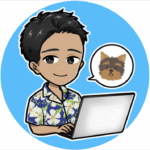
🌟一度きりの人生。周りを気にしすぎず、「自分の人生を生きよう」という思いを込めて。
お金・健康・グルメについて発信しながら、好きな時に好きな人とワイワイできる人生を応援します。
📌 経歴と活動
法人経営・不動産賃貸業(都内)
投資歴27年:高配当株・投資信託・iDeCo・NISA
大家歴20年:堅実な資産形成を実践
接客業歴30年:人とのつながりを大切に
🎯 モットー
『人は人、己は己』——比べる必要なし
『自分にしか決められない目標』を大切に
💡 興味・テーマ
資産運用(高配当株・投資信託・iDeCo・NISA)
健康・グルメ・ライフスタイルの質向上
「みんなでリッチに、健康に、幸せに」
🎉 趣味:麻雀・サウナ・料理・読書
特技:超絶旨いカレー作り
大切な時間:仲間とワイワイ・愛犬と過ごす時間
好きな食べ物:お鮨・お肉・お好み焼き
旅行スタイル:温泉宿でまったりと
🌈 メッセージ
「行動するか、しないか」——その小さな一歩が未来を大きく変えます。
一緒に明るい未来へ歩み始めましょう!
就職氷河期世代でも、行動すればなんとかなる✊
☆ 丸くなるな、星になれ
