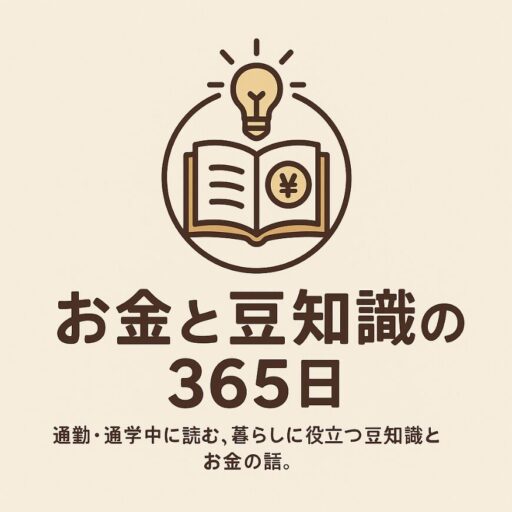こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日10月3日は、「登山の日」です。
澄んだ秋空、山の上から見下ろす紅葉のじゅうたん。
自然の中を一歩ずつ進むたびに、日常の喧騒が遠のき、心がふっと軽くなる――登山にはそんな不思議な魅力があります。
最近は、ハイキングや低山トレッキングを楽しむ人も増え、週末に気軽に山へ出かける方も多くなりました。
一方で、登山は美しい自然を楽しむだけでなく、安全への備えも欠かせないアクティビティです。
気象の急変や道迷い、体力不足によるトラブルなど、想像以上にリスクが潜んでいます。
だからこそ「登山の日」は、山を愛するすべての人にとって、自然と安全の両方を考えるきっかけの日でもあるのです。
今日は、山の魅力や歴史、そして登山を楽しむために大切なことを一緒に見つめ直してみませんか?
これから山へ行きたい人も、すでに登っている人も、知っておきたい豆知識がたくさんありますよ⛰️🍂
由来と制定の背景
- 「登山の日」は、日本アルパイン・ガイド協会(現:日本アルパインガイド協会)が1992年に制定。
- 日付は「と(10)ざん(3)」の語呂合わせから決まりました。
- 登山の魅力を広めると同時に、安全登山の啓発を目的としています。
- 日本記念日協会にも登録されており、登山文化と安全意識を広める記念日です。
日本の登山の現状
1. 登山人口の変化とアウトドアブーム
- 登山人口は1970〜80年代にかけてピークを迎え、その後減少しましたが、ここ10年で回復傾向。
- 健康志向、自然志向、SNSでの写真共有などが若年層の登山参加を後押し。
- 低山トレッキングやハイキング、登山×キャンプ(テン泊)など、ライトな山の楽しみ方が人気上昇中。
2. 高齢登山者の増加
- 登山者の平均年齢が上昇しており、60〜70代の参加が目立つ。
- 健康維持目的の登山が増えている一方、体力不足や持病による遭難リスクも増加。
- 遭難原因のトップは「道迷い」と「転倒・滑落」。
特に秋は日没が早く、ライト・防寒・行動計画不足によるトラブルが多発しています。
3. コロナ禍以降の変化
- コロナ禍で密を避けるレジャーとして登山・ハイキング人気が急増。
- 初心者が増えたことで、装備不十分や知識不足による事故件数が上昇。
- 同時に、登山アプリ(YAMAP、コンパスなど)を使う人が増え、情報共有が活発になりました。
登山の日に関連した取り組み
1. 安全登山の啓発活動
- 日本アルパインガイド協会や各山岳団体が、毎年10月を中心に安全登山キャンペーンを実施。
- 登山計画書の提出・GPSアプリ利用・装備点検などを呼びかけ。
- 講習会やオンラインセミナーで、初心者からベテランまで安全意識を高める取り組みが行われています。
2. 登山届システムの普及
- 従来は紙で提出していた登山届が、オンライン化・アプリ化(コンパス・YAMAP)により簡単に。
- 遭難時の捜索スピード向上や、計画的な登山の習慣化に貢献。
3. 山岳保険・救助体制の整備
- 山岳事故の高額な救助費用をカバーする山岳保険への加入が推奨されている。
- ドローンやGPSを活用した救助体制の整備も進んでいます。
4. 環境保全と持続可能な登山文化
- 富士山や北アルプスなど人気山域では、ゴミ問題やトイレ整備費用が課題。
- 一部の山域では「協力金制度(環境保全協力金)」が導入され、持続可能な登山環境を整える取り組みが進行中。
- 外来植物の駆除や登山道の修復など、ボランティア活動も活発化。
5. 地域振興と山岳観光
- 登山ブームに合わせて山小屋のリニューアル、登山口の整備、山岳鉄道・バスの観光化が進む。
- 登山と温泉、地元グルメを組み合わせた地域活性化モデルが各地で拡大。
「登山の日」は、山を愛する人が自然の魅力を再発見すると同時に、安全・環境保全を考えるための日です。
登山人口が増える中で、事故防止と自然との共生がこれからの大きなテーマになっています。
登山の日が持つ意味・課題
- 自然と共生する文化を伝える日
山をただ登るだけでなく、自然を守る心を育てる機会。
- 安全登山の意識を高める日
装備、天候判断、体調管理など、基本を見直すきっかけに。
- 地域振興と観光の可能性
登山道整備や山小屋文化が観光資源として注目されている。
- 課題は遭難の増加と環境保全
高齢化・ライト層の増加で事故が増え、ゴミ問題や山の荒廃も課題。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
誰かに話したい雑学
1. 日本の山はおよそ1万7000座以上
- 国土地理院の地図上で確認できる山の数は1万7000座以上。
- 高さも形もさまざまで、3000m級は本州の中部山岳地帯(北・中央・南アルプス)に集中しています。
2. 日本一高い山は富士山だけど「測り方」にも歴史あり
- 富士山は標高3776.12m(国土地理院2023年発表)。
- 江戸時代には三角測量がなく、当時の推定値は約3800mとされていたこともあります。
3. 「日本百名山」は一人の登山家が選んだ
- 日本で人気の「百名山」は、作家・登山家の深田久弥が著書『日本百名山』(1964年)で選定。
- 標高だけでなく「山の品格」「歴史」「個性」などを総合的に判断して選ばれています。
4. 日本人初のエベレスト登頂者は植村直己ではない
- 実は日本人初のエベレスト登頂は松浦輝男・杉山隆(1970年)。
- 有名な植村直己は世界初の「北米・南米・アフリカ・ヨーロッパ・アジアの五大陸最高峰登頂」を達成した冒険家です。
5. 遭難原因のトップは「道迷い」
- 日本の山岳遭難の約4割が道迷い。
- 体力不足・滑落・転倒が続きます。地図アプリ+紙地図の併用が安全のカギです。
6. 山小屋文化は日本独特
- 北アルプスや富士山などでは山小屋泊が一般的。
- 海外の山岳地帯ではテント泊が主流の地域も多く、日本の山小屋は食事や寝具が整っている快適さで有名です。
7. 登山のカロリー消費は想像以上
- 標準的な登山では1時間に約400〜600kcal消費。
- 1日6〜8時間歩くと、1日分の摂取カロリーをほぼ使い切るレベルの運動量になります。
8. 富士山は活火山
- 最後の噴火は宝永4年(1707年)。
- 活火山の中でも今後の噴火リスクが指摘されており、ハザードマップの更新や防災訓練が行われています。
9. 登山届はオンライン提出が主流に
- コンパス、YAMAPなどのアプリを使えばスマホから登山届が提出可能。
- 遭難時の位置特定や捜索時間短縮に大きく貢献しています。
10. 世界一登られている山のひとつは高尾山
- 東京・八王子にある高尾山は年間約300万人以上が訪れる世界的な人気登山スポット。
- 都心からアクセスが良く、初心者からベテランまで楽しめるコースが充実しています。
「今日の“今日は何の日”は「登山の日」でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」
ABOUT ME
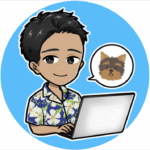
🌟一度きりの人生。周りを気にしすぎず、「自分の人生を生きよう」という思いを込めて。
お金・健康・グルメについて発信しながら、好きな時に好きな人とワイワイできる人生を応援します。
📌 経歴と活動
法人経営・不動産賃貸業(都内)
投資歴27年:高配当株・投資信託・iDeCo・NISA
大家歴20年:堅実な資産形成を実践
接客業歴30年:人とのつながりを大切に
🎯 モットー
『人は人、己は己』——比べる必要なし
『自分にしか決められない目標』を大切に
💡 興味・テーマ
資産運用(高配当株・投資信託・iDeCo・NISA)
健康・グルメ・ライフスタイルの質向上
「みんなでリッチに、健康に、幸せに」
🎉 趣味:麻雀・サウナ・料理・読書
特技:超絶旨いカレー作り
大切な時間:仲間とワイワイ・愛犬と過ごす時間
好きな食べ物:お鮨・お肉・お好み焼き
旅行スタイル:温泉宿でまったりと
🌈 メッセージ
「行動するか、しないか」——その小さな一歩が未来を大きく変えます。
一緒に明るい未来へ歩み始めましょう!
就職氷河期世代でも、行動すればなんとかなる✊
☆ 丸くなるな、星になれ