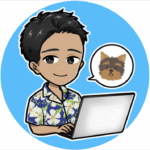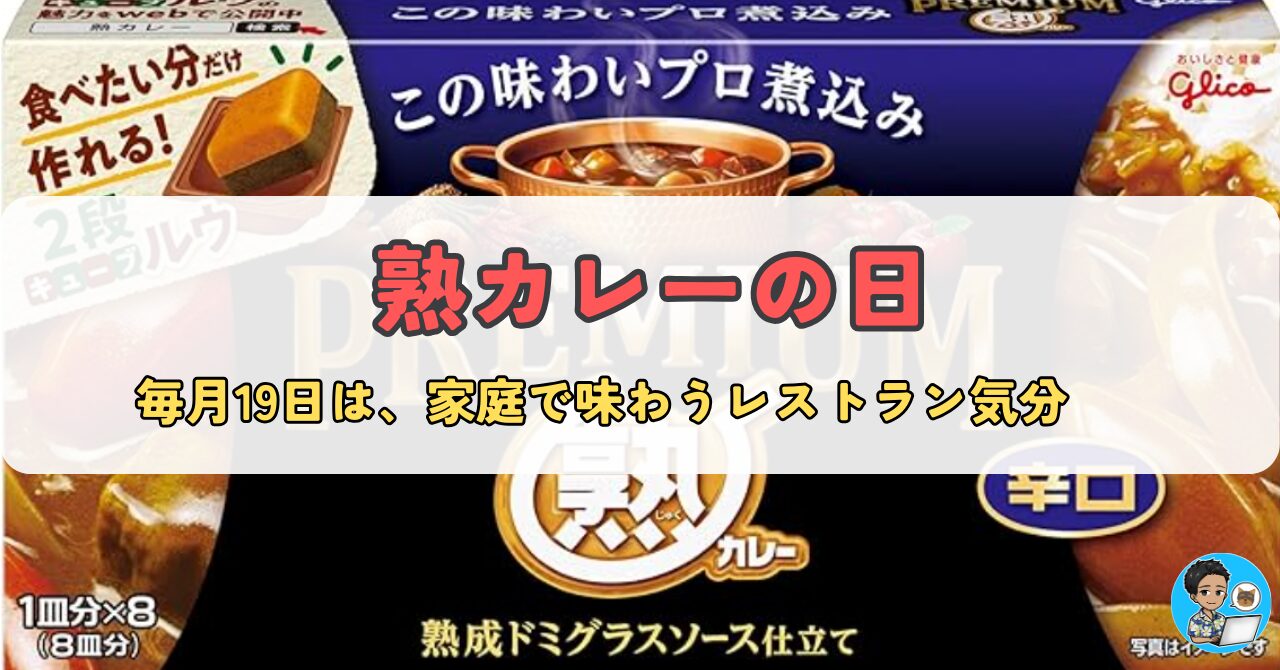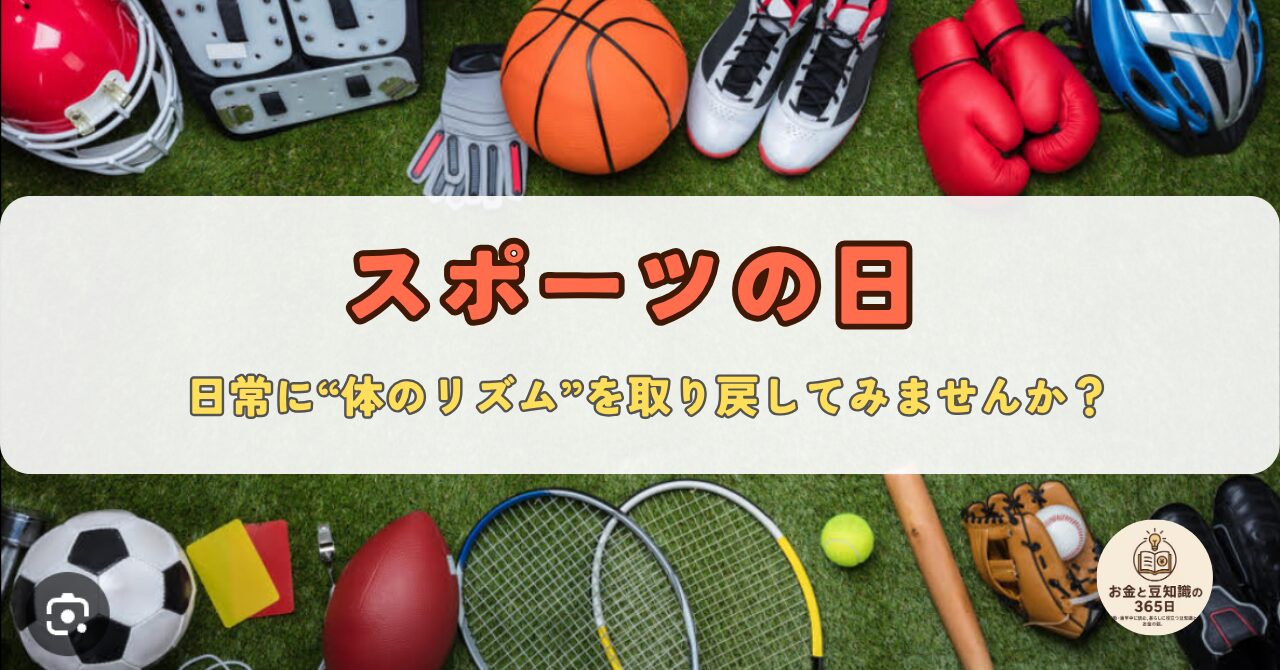9月15日【敬老の日】─ありがとうを伝える、その一日が教えてくれること

こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
今日は敬老の日。あなたの「おじいちゃん・おばあちゃん」も、もちろん近所のお年寄りも含めて――多くの人に“感謝”を伝える日です。
「いつもありがとう」「あなたのおかげで今があります」そんな気持ちを、言葉だけじゃなく行動で伝える。少し立ち止まって、敬老の日の由来や意義を知ると、感謝の気持ちがもっと深まるはずです。
歴史と由来
- 敬老の日は「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨とした国民の祝日。
- 起源は兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町)で1947年(昭和22年)9月15日に「敬老会」を開いたこと。村長の門脇政夫氏が「老人を大切にし、年寄りの知恵を借りよう」という思いから始まった儀式でした。
- その後、「としよりの日」として広まり、1950年に県の行事、1966年に「敬老の日」として国民の祝日として制定。 当初は毎年9月15日でしたが、2003年から「9月の第3月曜日」となるよう法律が変わりました(ハッピーマンデー制度の導入)
ちょこっと豆知識を深掘り!【敬老の日 編】
1. 「敬老の日」は“世界的に見ても珍しい”祝日⁉
実は、高齢者を対象にした国民の祝日を持つ国は、世界的にはかなり少数派。
日本の「敬老の日」は、国をあげて高齢者への感謝を示すという点で、とてもユニークな制度なんです。
欧米では“Grandparents Day(祖父母の日)”が存在する国もありますが、国民の祝日として定着しているのは日本くらい。
つまり、敬老の日は「世界に誇れる、日本ならではの文化」でもあるのです。
2. 何歳から“敬老”される?実は決まりはナシ!
「敬老の日って、何歳からお祝いされるの?」と聞かれることも多いですが…
実は、明確な年齢制限は一切ナシ!
- 年齢ではなく「多年にわたり社会に尽くしてきた人」が対象。
- 一般的には70歳以上を目安にすることが多いですが、
自治体や家庭、職場によっては60歳・65歳・75歳などバラバラ。
つまり、“気持ち”が伝わればそれでOKなんです😊
3. なぜ「9月15日」→「第3月曜日」になったの?
もともとは9月15日だった「敬老の日」ですが、2003年から「9月第3月曜日」に移行しました。
これは「ハッピーマンデー制度」によるもの。
ではなぜ9月15日だったのか?
その背景には、以下の理由があるとされています👇
- 農作業が落ち着く「農閑期」で行事に適していた
- 天候が比較的安定しやすく、集まりやすい時期だった
- 兵庫県の村で最初に「敬老会」が開かれたのがこの日だった
実は、**天気や地域の生活リズムが考慮された“生活密着型の記念日”**だったんですね。
4. 昔は「としよりの日」だった!
1947年に始まった当初は、なんと「としよりの日」という名称でした。
その後、名称が「老人の日」に変わり、最終的に「敬老の日」へ。
語感が優しく、相手に対する敬意がこもった表現として今の名称に定着したわけです。
高齢化社会の中で、呼び方ひとつにも配慮と変化が見られます。
5. プレゼントの定番、実は時代で変化してる?
一昔前は“ちゃんちゃんこ”や“湯呑み”が定番でしたが、
今では「一緒に過ごす時間」や「体験型ギフト」が人気上昇中!
- 家族写真を入れたフォトフレーム
- 温泉旅行やグルメギフト
- 孫とのビデオメッセージなども喜ばれます📹
“モノ”から“想い出”へ。
そんなプレゼントの変化にも、時代の価値観が表れていますね。
敬老の日が“今”に伝える、大切なこと【現代につながる意義】
1. 高齢化が進む日本で、“世代間の架け橋”となる日
日本は世界有数の超高齢社会。
65歳以上の人口は3,600万人を超え、全体の約30%に(総務省統計より)。
そんな時代だからこそ、敬老の日は単なる「祝日」ではなく、
**高齢者と若い世代がつながる大切な“対話のきっかけ”**になっています。
- 普段なかなか会えないおじいちゃん・おばあちゃんに連絡する
- 昔話を聞いて、“人生の知恵”を学ぶ
- 家族や地域の歴史を再確認する
こうした行動を通じて、世代を超えた絆が育まれる日となっているのです。
2. “感謝の見える化”が、心の健康にもつながる
実は、高齢者にとっては「感謝される」「存在を認められる」ことが、
うつ予防や認知症の進行緩和にもプラスに働くとする研究結果もあります。
つまり、孫からの「ありがとう」一言で、
心が軽くなったり、元気が出たりするというわけです。
敬老の日は、そんな**“こころの健康”を守る日**でもあるのです。
3. 地域コミュニティをつなぐ“あたたかいハブ”
敬老の日を活用して、各地の自治体や地域団体では:
- 地域の高齢者を招いた「敬老会」や演芸大会
- 小学校・保育園と連携したプレゼント作り
- 地元産品を贈る地域限定ギフト企画
などが行われています。
これにより、「顔の見えるつながり」が生まれ、
地域防災・孤立防止・支援ネットワークづくりにも貢献しています。
4. 変わりゆく価値観に応える“自由な祝い方”
- 昔は“お年寄りをねぎらう日”という印象が強かった敬老の日ですが、
現代では**「人生の先輩をリスペクトする日」**として定着。 - 年齢に関係なく、「お父さん・お母さん、いつもありがとう」と伝える家庭も増えています。
- ギフトの形も、“ちゃんちゃんこ”から“グルメ旅行・温泉・スポーツ用品・おしゃれグッズ”へ。
つまり今の敬老の日は、「年寄り扱いする」日ではなく「人生の功労をたたえる」日なんです。
5. 私たち自身の“未来”を見つめる日
今、私たちが敬老の日に感謝を伝える相手がいるように、
いつか自分も“敬われる側”になる日が来ます。
だからこそ、
- 「どんな年の重ね方をしたいか」
- 「どんなふうに家族と向き合っていきたいか」
- 「どんなふうに“感謝される人”でいたいか」
を考えるきっかけにもなります。
敬老の日は、**「誰かのための日」であり、「未来の自分への問いかけ」**でもあるのです。
敬老の日は、ただ「高齢者に優しくする日」ではありません。
つながりを深め、心を通わせ、未来の自分へも思いを巡らせる日。
そんな深い意味が、令和の今こそ、もっと大切にされるべきなのかもしれませんね。
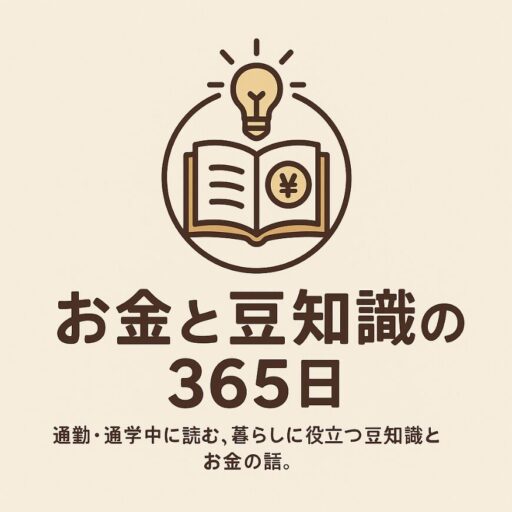
まとめ:「ありがとう」の一言が、心を動かす日。
敬老の日は、長年にわたり社会や家族を支えてきた方々に、
「ありがとう」や「おつかれさま」を伝える日。
でも、それは決して特別なことでなくて、
電話一本、メッセージ一通、笑顔の一言でもいい。
私たちが何気なく過ごす日常の中で、
“感謝をカタチにするチャンス”が、今日という日なのです。
そしてそれは、
高齢者を敬うだけでなく、自分自身の未来を思いやることにもつながります。
だからこそ、
今年の敬老の日は、“少しだけ丁寧な心”で過ごしてみませんか?