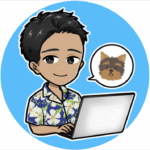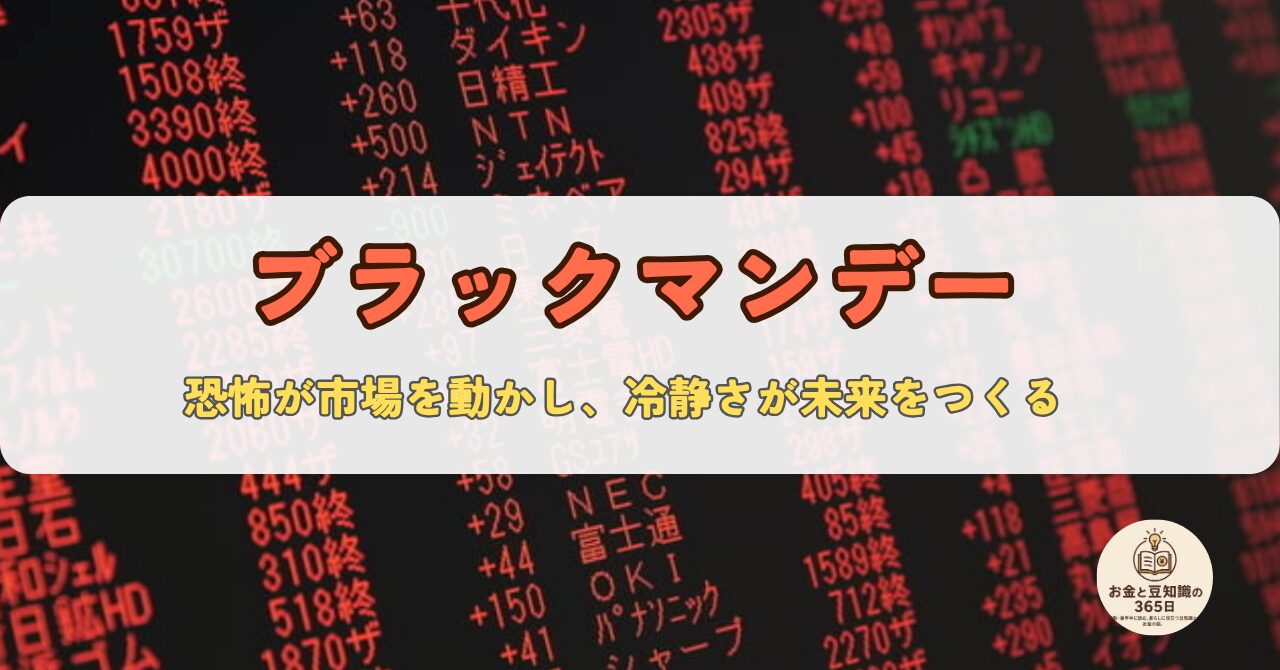9月26日【大腸を考える日】苦労をなくし、くつろぐ毎日へ―
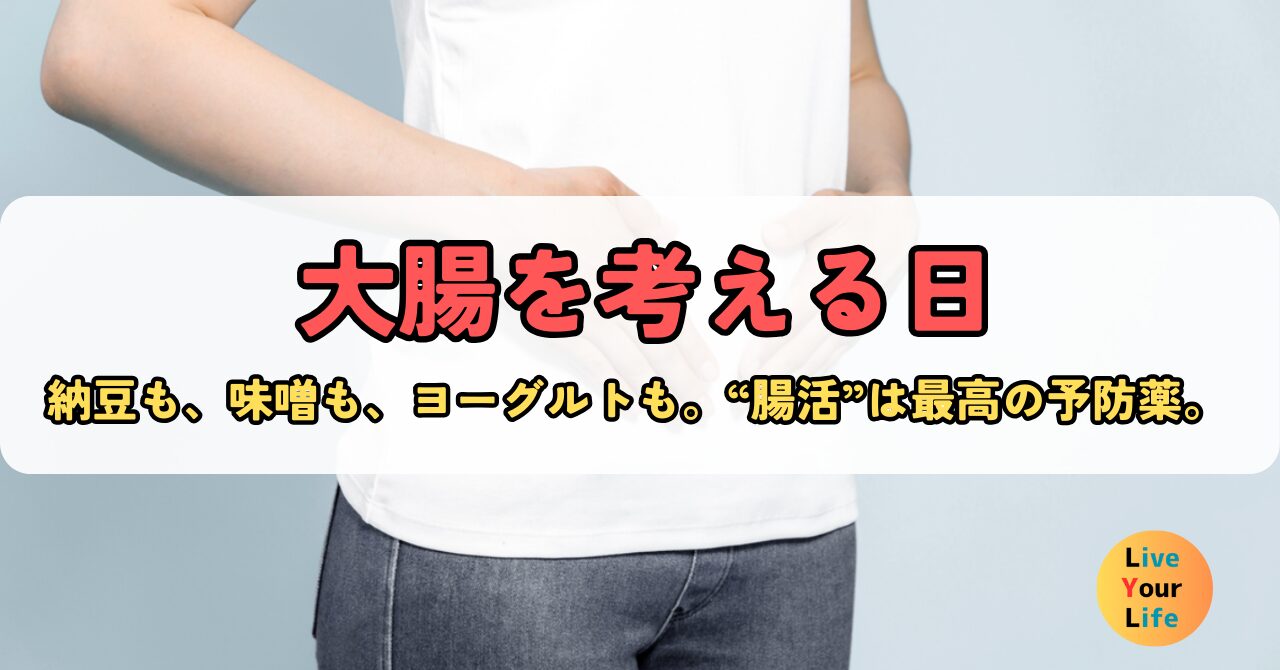
こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日9月26日は、「大腸を考える日」です。
私たちの体の中で、毎日休まず働いている“腸”。特に大腸は、消化の仕上げや水分吸収、免疫機能など健康全般に直結する重要な臓器です。
でも普段はあまり意識する機会がないかもしれません。今日はこの記念日をきっかけに、大腸と健康について考えてみましょう。
「大腸を考える日」とは?その背景と意義
由来と制定の背景
- 「大腸を考える日」は、日本大腸検査学会が2006年に制定した記念日。
- 日付は 9月26日。語呂合わせで「9(く)2(つ)6(ろ)=苦労」と読めることから、「大腸の病気や治療による苦労を減らそう」という願いが込められています。
- 大腸がんをはじめとする疾患の予防啓発と、検査・健診の受診を広げることが目的です。
- 日本記念日協会にも登録されています。
毎日の疲れやお腹の不調、便秘やお通じの乱れ…そんな悩みを感じているなら、まずは腸を整えることが近道。
生菌活 フローラ Premium 90日分(30日 × 3袋) が選ばれる理由はここ
乳酸菌 20兆個+26種の多様な菌株を配合 → 腸内フローラを幅広くサポート
酪酸菌 5億個配合で短鎖脂肪酸の生成をバックアップ
国内製造・品質管理体制が信頼できる
まとめ買いできる 90日分セットで“始めやすさ”も配慮
👉【生菌活 フローラ Premium の詳細・価格をチェックする】

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、体調・メンタル・肌状態にも影響を与えるとも言われます。まずは 3日、7日、2週間…変化を感じてみて。
「大腸を考える日」の現状と取り組み
1. 日本における大腸がんの現状
- 日本では がんによる死亡原因の上位が大腸がん。
- 女性では死亡原因の第1位、男性でも上位に位置しています。
- 年間の罹患者は 約15万人、死亡者は 5万人超。
- 特に40代後半からリスクが高まり、50歳以上は要注意とされています。
2. 学会・医療機関の取り組み
- 便潜血検査の普及
- 健診で配布される採便検査。安価で簡便だが受診率はまだ6割程度。
- 大腸内視鏡検査の推進
- ポリープの段階で発見・切除できるため、早期発見・予防効果が高い。
- 大腸検査の啓発イベント
- 「大腸を考える日」に合わせ、医療機関や学会が講演会・公開セミナー・無料相談を開催。
- メディア発信
- テレビや新聞で「腸活」「腸内環境」の特集が組まれるなど、広報活動も積極的。
3. 社会的な取り組み
- 自治体の検診推奨
- 各市区町村で40歳以上を対象とした便潜血検査を実施。
- 一部自治体では大腸内視鏡検査費用の助成制度もあり。
- 企業の健康経営
- 健康診断で大腸検査を必須化する企業も増加。
- 働き盛り世代の受診率向上に貢献。
- 患者会・NPOの活動
- 罹患者や家族による交流・情報共有の会が全国各地で開催され、正しい知識の普及に一役。
4. 生活習慣と「腸活」ブーム
- 食生活改善
- 食物繊維の摂取(野菜・海藻・豆類)
- 発酵食品(ヨーグルト・納豆・味噌)で腸内環境改善
- 運動習慣
- 運動不足は大腸がんリスクを高める。ウォーキングや軽い筋トレが推奨される。
- 腸活ブーム
- 雑誌やSNSで「腸活レシピ」や「発酵食品生活」が紹介され、若い世代にも広がりを見せている。
5. 今後の課題
- 受診率の低さ
- 便潜血検査・大腸内視鏡の受診率はまだ十分とは言えず、特に男性の中高年に多い「未受診層」が課題。
- コロナ禍での受診控え
- 2020〜2022年にかけて、健診受診率が一時的に低下。発見の遅れが懸念されている。
- 啓発の継続性
- 「腸活」はブームで終わらせず、検診や生活習慣改善につなげる取り組みが必要。
大腸を考える日が持つ意味・課題
- 早期発見・早期治療の重要性
大腸がんは早期に発見できれば治癒率が非常に高い。 - 生活習慣病予防
食物繊維不足、運動不足、過度な飲酒やストレスがリスク因子。 - 検診受診率の向上
便潜血検査や内視鏡検査の受診率はまだ十分とはいえず、意識向上が課題。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
1. 大腸の長さは約1.5m
- 小腸(約6〜7m)に比べると短いけれど、水分吸収・便の形成・腸内細菌の活動拠点として欠かせない臓器。
- 大腸内には 数百兆個の腸内細菌が存在すると言われ、免疫や精神状態にも影響する。
2. 大腸がんは「日本人に最も多いがん」の一つ
- 毎年 約15万人が罹患、約5万人が死亡。
- 特に女性では がん死亡原因の第1位(男性も上位)。
- ただし 早期発見すれば90%以上が治癒可能という特徴がある。
3. 大腸がんのリスク因子
- 食生活:赤肉・加工肉の過剰摂取がリスク増。WHOも発表済み。
- 運動不足、肥満、飲酒、喫煙も関連。
- 一方で 食物繊維・カルシウム・ビタミンDの摂取は予防効果があるとされる。
4. 「腸は第2の脳」と呼ばれる
- 腸には約1億個もの神経細胞があり、自律的に働く仕組みを持つ。
- 脳からの指令がなくても腸は動き続けるため、「セカンドブレイン」と呼ばれている。
- セロトニン(幸せホルモン)の9割以上は腸で作られるという研究もあり、心の健康とも直結。
5. 日本の検診受診率はまだ低い
- 欧米の大腸内視鏡受診率は50〜60%程度あるのに対し、日本ではまだ20%台。
- 便潜血検査は簡単で費用も安いのに、未受診者が多いのが課題。
6. 発酵食品と腸内環境
- 日本の伝統食(納豆、味噌、漬物)は「腸に優しい食品」の宝庫。
- ヨーグルトやチーズなど乳酸菌食品も効果的。
- 最近は プロバイオティクス(善玉菌を摂る)+プレバイオティクス(善玉菌のエサを摂る) の組み合わせ=シンバイオティクス が注目。
7. 9月26日は「くつろぐ日」でもある?
- 「9(く)2(つ)6(ろ)」=「くつろぐ」と読めることから、
「腸の健康を守って、心身ともに“くつろぐ”生活を」という意味を込めた紹介がされることもある。 - 「苦労をなくす」と同時に、「くつろぐ」につなげるユーモアある記念日なんです。
まとめ
「大腸を考える日」は、私たちの体の“要”である大腸について 知る・考える・行動する きっかけを与えてくれる日です。
大腸がんは日本人にとって身近ながんのひとつですが、早期発見すれば90%以上が治癒可能。
だからこそ、検診を受ける習慣や、腸をいたわる生活習慣(腸活)がとても大切です。
9月26日は、「苦労をなくす」「くつろぐ」とも読めるユーモアある日。
検診の予約を入れるのもよし、発酵食品を取り入れるのもよし、ウォーキングを始めるのもよし。
今日をきっかけに、“腸から健康を育てる”第一歩を踏み出してみませんか?
「今日の“今日は何の日”は「大腸を考える日」でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」