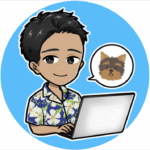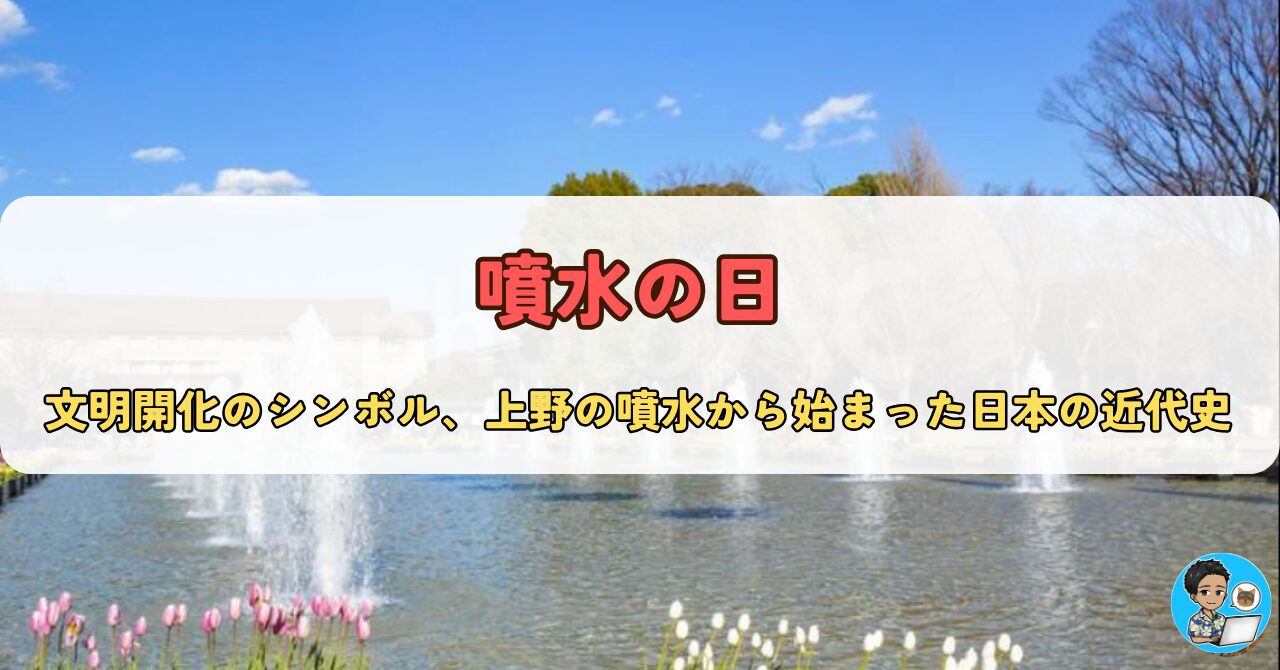10月21日は「早稲田大学創立記念日」|“学問の独立”を掲げた志の原点

こんにちは!毎日更新「今日は何の日コーナー」へようこそ。
本日10月21日は、早稲田大学の創立記念日です。
1882年(明治15年)のこの日、政治家・教育家である大隈重信が、
「国家を担う人材を育てる」という強い信念のもとに
東京・牛込(現在の新宿区早稲田)に東京専門学校を創立しました。
それが、のちの「早稲田大学」となり、
140年以上にわたって日本の学問・文化・スポーツ・社会をリードしてきたのです。
💬 “学問の独立、学の活用、模範国民の造就”
――この言葉が、早稲田のすべての原点です。
由来と制定の背景
創立:1882年10月21日
1882年(明治15年)10月21日、
大隈重信が私財を投じて「東京専門学校」を設立。
これが早稲田大学の起点となりました。
彼は当時、自由民権運動が盛んだった日本で、
“自立した知識人”を育てることの必要性を痛感していたのです。
「真理を探究し、国家のために尽くす」
――その理念が、早稲田の精神として今も受け継がれています。
「大学」への発展
1902年に「早稲田大学」と改称し、
その後、文学部・法学部・政治経済学部などを開設。
大隈重信の“進取の精神”のもと、
自由で多様な教育環境を築いていきました。
現在では学生数約5万人、卒業生は世界中に広がり、
多くの政治家・文化人・起業家・研究者を輩出する総合大学として知られています。
現状と取り組み
グローバル大学としての進化
21世紀の早稲田大学は、
「世界に開かれた大学」を目指して、
国際教育プログラムや留学生受け入れに積極的です。
- 交換留学協定校は 約90か国・地域、700校以上
- 英語のみで卒業できる学部(SILS、政治経済学部など)を設置
- 海外拠点(シンガポール・北京・台北など)を展開
こうした動きは、“世界の早稲田”としての存在感を高めています。
研究・イノベーション
AI、量子科学、脱炭素技術、人文社会科学――
分野を超えた研究が進む中、
早稲田は「社会課題をデータで解く大学」としても注目されています。
たとえば、
- スマートシティ実証プロジェクト
- 生成AI倫理研究センターの設立(2024)
- グリーン・トランスフォーメーション研究拠点
など、学問を社会に還元する取り組みを加速中です。
文化・スポーツの名門として
“早稲田と慶應”といえば、誰もが思い浮かべる早慶戦⚾
野球をはじめ、駅伝、サッカー、ラグビーなど、
学生スポーツ文化の象徴的存在でもあります。
その根底にあるのは、「文武両道」と「誠実な挑戦」。
単なる勝敗を超えた「努力と友情のドラマ」が、今もキャンパスに息づいています。
豆知識・“へぇ〜”ポイント
① “早稲田”の名前の由来
早稲田の地名は、文字通り「早く稲が実る田」に由来。
大隈重信がこの地を選んだのは、
「若者の成長が早く実を結ぶように」との願いを込めたともいわれています🌾
② 校歌「都の西北」は学生たちの手によるもの
早稲田大学の校歌「都の西北」は、
作詞:相馬御風、作曲:東儀鉄笛。
学生たちの情熱が結晶となって誕生しました。
“都の西北 早稲田の杜に〜♪”
いまも創立記念式典などで高らかに歌い継がれています。
③ 大隈重信像の右足が“金色”の理由
早稲田キャンパスのシンボル・大隈重信像の右足が輝いているのは、
「触ると合格・成功する」という学生たちのジンクス。
多くの受験生や卒業生が、願掛けにそっと触れていくのです。
④ “進取の精神”とは?
「進取(しんしゅ)」とは、“自ら進んで新しいことに挑む”という意味。
大隈が掲げた教育理念の中心であり、
今でも早稲田の教育方針や研究姿勢に深く根づいています。
⑤ 創立記念日は“授業休講日”
10月21日は、早稲田大学の公式な休講日。
キャンパスでは記念式典が行われ、
学内外の関係者が建学の精神を振り返ります。
まとめ ― 早稲田は“挑戦する知”の象徴
10月21日「早稲田大学創立記念日」は、
単なる大学の誕生日ではありません。
それは、
“学問の自由と社会貢献”を両立させた、日本の知の出発点。
早稲田が140年以上にわたり築いてきたもの――
それは、時代の変化に流されず、常に挑戦し続ける精神。
「進取の気象」という言葉に象徴されるように、
早稲田は常に“昨日よりも新しい自分”を目指し続けています。
💭 ひとことで言うと:
「早稲田の原点は、“自由に学び、社会を動かす勇気”。」
大隈重信が夢見た“新しい日本の姿”は、
いまもキャンパスの風の中に息づいているのです。
「今日の“今日は何の日”は「早稲田大学創立記念日」でした。明日はどんな一日になるでしょうか?またこの場所でお会いできるのを楽しみにしています!」